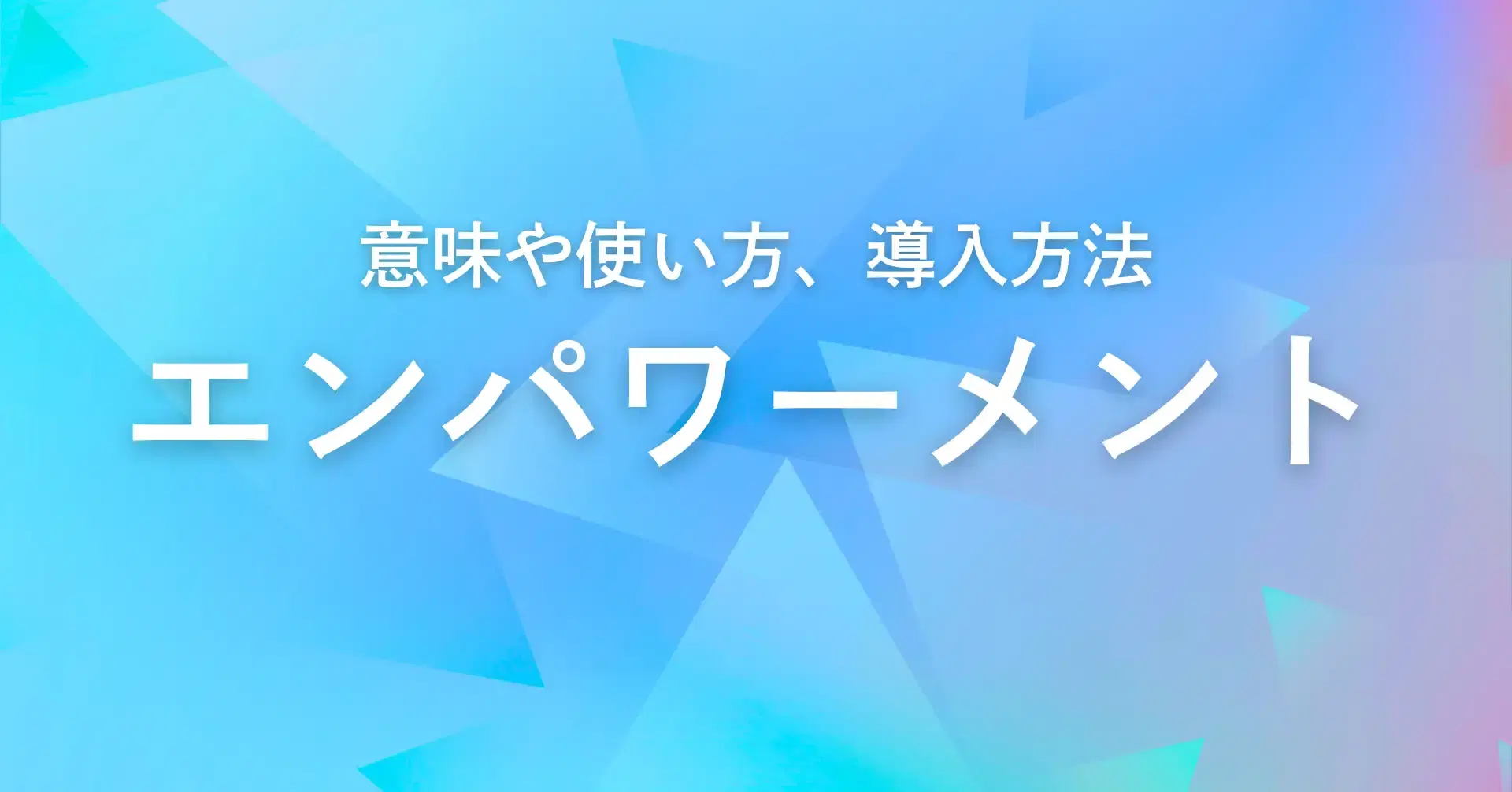目次
■おすすめ転職サイト
サイト名 | 特徴 | 詳細 |
|---|---|---|
ハイクラス×ベンチャー専門転職なら! | ||
日本最大級の転職サイト | ||
ハイクラス専門転職なら! | ||
業界最大数の求人数 |
※時間がない方へ・・記事を読む時間が無い方でバックオフィス系の転職を検討中の方は、まずは「WARCエージェント」に無料登録してみましょう!
エンパワーメントとは
エンパワーメントとは、組織を構成する一人ひとりが本来持っている力を最大限に発揮し、自らの意思決定により自発的に行動できる状態を言います。英語のempower(エンパワー)からできた言葉です。
もともとエンパワーメントとは、「能力開発」という意味で捉えられ、人材育成やマネジメント手法の一つとして注目されていました。また、本来ならば管理者が持つであろう権限を部下に託し、仕事の進め方や意思決定を自発的に行わせる「権限委譲」という意味でも捉えることができます。
このように、従来の組織体制の中で与えられた仕事だけを行うのではなく、積極的に部下に権限や挑戦の機会を与えることをエンパワーメントが大切です。その結果、従業員一人ひとりが個人の能力を最大限に活かすエンパワーメントが発揮され、組織の成長にも寄与する効果があります。
エンパワメントの原則
エンパワーメントを取り入れる際に重要なのが、エンパワーメントの8つの原則です。以下に記載されている8つの原則を意識することで、従業員の能力を効果的に引き出せるといわれています。
エンパワーメントの8原則(※1)
- 目標を当事者が選択する
- 主導権と決定権を当事者が持つ
- 問題点と解決策を当事者が考える
- 新たな学びと、より力をつける機会として当事者が失敗や成功を分析する
- 行動変容のために内的な強化因子を当事者と専門職の両者で発見し、それを増強する
- 問題解決の過程に当事者の参加を促し、個人の責任を高める
- 問題解決の過程を支えるネットワークと資源を充実させる
- 当事者のウエルビーイングに対する意欲を高める
エンパワーメントと一概に言っても、分野によって概念が異なります。しかし、どの分野でも、エンパワーメントの8原則を意識することが重要です。
(※1)参考:J-Stage「◆エンパワメントの理論と技術の活用―変化に対処し、 次の発展を生み出す力 ―」
エンパワーメントの起源
エンパワーメントは、もともと1970年代のアメリカで起こった公民権運動や、1980年代の女性権利獲得運動の中で使われた考え方です。社会運動の高まりと共に、一人ひとりが本来持つ権利や人格を保つための力を身に付けること、能力が発揮できる社会を目指すべきだと広く提唱されました。
始まりは社会運動から生まれた社会的地位に対する考え方ですが、現在では福祉や介護、教育分野などでも利用されています。地位の向上や自立促進を目指す考え方は、変化が激しい現代において、ビジネスでも注目されるようになったのです。
グローバル化やITの進化など、企業には柔軟な対応が求められます。その際必要なのが、そこで働く従業員の高い能力です。それらを引き出すことが、エンパワーメントであり、今後も注目され続けることが予測できるでしょう。
それぞれの分野でのエンパワーメント
エンパワーメントは概念によって、分野が異なります。どのような分野がエンパワーメントに存在するのでしょうか。以下では、それぞれの分野別に紹介します。紹介されている分野を参考にエンパワーメントに対する理解をさらに深めてみましょう。
ビジネスでのエンパワーメント
ビジネスにおけるエンパワーメントには、「自律性促進」「権限移譲」「能力開花」という考えが使われています。
たとえば、本来であれば上司が行ってた意思決定や業務遂行方法の決定を部下に任せることなどがイメージしやすいのではないでしょうか。これまでなかった権限や責任を与えられることで、結果的に個人の自律性を促進し、潜在能力を最大限に発揮させることを目的としています。
もちろん、急な権限委譲だけではなかなかうまくいかず、かえって自信を無くしてしまう従業員もでてきてしまう可能性も少なくないです。上司はこのようなリスクを防ぐために、権限委譲と一緒に1on1などのフォローを実施しましょう。部下の意見を尊重しながら、目標達成に向けたサポートができれば、エンパワーメントを効果的に引き出すことができます。
従業員のエンパワーメントを最大限に引き出すことは、従業員の成長、さらには企業の成長にもつながるので効果的です。
教育分野のエンパワーメント
教育分野におけるエンパワーメントは、「子どもの知識欲刺激」「自発的な行動力を伸ばす」という意味で使われています。
多くの子どもが、学校の宿題やテストのためだけに勉強をしてしまいがちです。その結果、子どもの勉強意欲を削いでしまう可能性が少なくありません。そこで、教育現場では子どもの好奇心を否定せず、自らが興味を持ったことを調べて、試行錯誤の中で失敗や成功を繰り返す経験を大切にすることが求められるようになりました。これが、教育現場でのエンパワーメントです。
この考えは、自ら選択と判断を行い、行動に移すことで、今後の生きる力を育むことにもつながると考えられています。
看護・介護分野のエンパワーメント
看護や介護分野におけるエンパワーメントは、「患者が主体的であるプロセス構成」の考え方が使われています。従来の看護や介護業界では、医師や看護師が主体となって動くのが一般的でした。そこに、患者がついていく受け身体制が多く、患者本人やその家族の意向が反映されにくかった課題が多かったです。
しかし、本来であれば看護や介護において1番の目的は患者の身体的・精神的独立ではないでしょうか。本来の目的を遂行するためには、患者が主体的となり、自ら意志で治療に参加する必要があります。
そこで、近年では医師や看護師は患者に正確な情報を提供した上で、患者の積極的な参加を促すようになりました。患者と十分なコミュニケーションを取り、患者の意思を尊重することでこれらは成り立ちます。
このような考えを、看護や介護分野におけるエンパワーメントとして考えられているのです。
障害者福祉分野のエンパワーメント
障害者福祉分野におけるエンパワーメントは、「それぞれの得意分野の発見、その力を伸ばす」という考え方で使われています。福祉の対象となる人の中には、障害を抱えている部分を除けば、健全者と能力が変わらない人が多いです。中には健全者以上の能力を兼ね備えている人もいます。
しかし、障害者を庇護すべき人間として扱ってしまうことで、本来発揮できるはずの能力開花の機会を奪ってしまう可能性が高いです。そこで、福祉の現場では本人が困っていることを援助しながら長所を伸ばし、障害を抱えている人たちに自信をつけてもらうことを大切にしています。これまで、苦手な分野や不足している力を平均値まで引き上げることに注力していましたが、エンパワーメントをきっかけに長所に目を向けるようになったのです。
エンパワーメントが注目される理由
なぜ、エンパワーメントが注目されるようになったのでしょうか。ビジネスや教育、介護や福祉などあらゆる分野で注目されるその理由について、以下で解説します。エンパワーメントが注目される理由を知れば、エンパワーメントのメリットにもつながるはずです。エンパワーメントに興味を持っている方は、参考にしてください。
次世代人材育成の重要性
エンパワーメントの考え方であれば、若手のうちから裁量の大きな環境で力を伸ばすことができ、次世代人材の育成につながります。特にビジネス分野でのエンパワーメントは、人材不足の現代において重要です。
これまでは、上司が裁量や権限を持ち、若手のうちはできるだけ小さな裁量で、長期的な計画のもと育成していくのが一般的でした。しかし、終身雇用がなくなり、転職や副業が当たり前になり、さらに人材不足が課題視されている現代において、長期的に人材育成は効率が悪いと考えられるようになったのです。企業は「できるだけ早く一人立ちしてほしい」「即戦力が欲しい」と望み、その結果人材育成の早期化が加速しました。
若手のうちから十分な能力を身に付けてもらうためには、権限を移譲し、迅速かつ柔軟な判断力などを身に付けられるエンパワーメントを発揮できる環境が重要だと考えられたのです。
VUCA(ブーカ)時代の到来
VUCA時代とは、VUCAとはVolatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguityの頭文字を取った造語で、「先行きが不透明で、将来の予測が困難な状態」を言います。2020年に流行した新型コロナウイルスをきっかけに、あらゆる事態が予測できない不安定なものになりました。中でも、ビジネスを取り巻く環境の変化は大きく、経営や業界は予測できないものになったのです。
こうした予測できない時代の中で、企業は時代の変化に対応しながら新たな価値を生み出せる、主体的かつ自律的な行動を求める人材を必要としています。上司の意見をそのまま実行するタイプではなく、自分で考えながら迅速な対応や判断ができるタイプの人材が重要なのです。
その際、エンパワーメントの考え方である「能力開花」や「権限委譲」は、組織にいる一人ひとりが抑圧されることなく、能力を発揮できるようになるため、エンパワーメントは注目されています。
エンパワーメントの使い方
エンパワーメントには以下のような使い方があります。
- エンパワーメントを図ることで、メンバーの能力開花を促す
- 部下へ権限委譲とフォローを行い、エンパワーメント経営を推進する
- 従業員エンパワーメントして能力を最大限に引き出すことで、企業の成長にもつながる
前述してきたように、エンパワーメントとは組織を構成する一人ひとりが本来持っている力を発揮すること、自らの意思決定により自発的に行動できるようにするという意味です。英語のempowermentは名詞形ですが、「力を与える」enpower(エンパワー)として動詞で評価されることもあります。
エンパワーメントのメリット
さまざまな分野で注目されているエンパワーメントですが、実際にエンパワーメントを実施することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。以下では、エンパワーメントを利用するメリットについて、3つにまとめています。メリットを理解し、エンパワーメントについて理解を深めてみましょう。
主体性の向上
エンパワーメントを実践すれば、主体性ある従業員の増加が期待できます。
仕事の権限を自分に与えられるということは、自らが下した決断に対して責任が発生するということです。これまでは、上司が庇ってくれていた部分も、自己責任になる部分がでてくるでしょう。そうなれば、これまで以上に問題が起きた際の原因を考えるようになり、未然にトラブルを防ぐためにさまざまな対策をするはずです。その結果、自分で考え行動できる主体性が生まれます。万が一の時にも仕事全体の流れを理解しながら、自分で課題解決ができるようになるのです。
仕事への当事者意識が高まると、仕事に対する積極性だけでなく、上司への不満が軽減される効果もあり、職場環境改善につながったケースも少なくありません。
業務スピードや生産性の向上
企業にエンパワーメントが導入されれば、業務スピードを格段にあげることも可能です。
ビジネスにおいて意思決定はさまざまな場面で発生します。その際、毎回上司に確認をしていると時間がかかってしまい、お客さまを待たせてしまう可能性が高いです。また、ビジネス機会を逃してしまうケースも少なくありません。しかし、エンパワーメントが導入されれば、急を要する案件に対して部下が自ら判断し、行動することができます。
これまで上司の判断を仰ぐための確認・指示待ちの時間を削減することができ、スピード感を持って業務に遂行できるのです。また、業務効率向上が実現できれば、お客さまを待たせる時間が減り、顧客満足度向上にもつながるでしょう。
そういった意味で、エンパワーメントは企業価値向上に寄与すると言えます。
モチベーションの向上
若手のうちから権限や裁量を与えられることで、仕事に対するモチベーションが上がる点もエンパワーメントのメリットです。
権限を持てば、自分で考えて行動したことがそのまま結果として表れます。もちろん、失敗することもありますが、その都度何が悪かったか自分で原因を突き詰めながら改善することで、能力向上につながるでしょう。その結果、自己成長を実感し、仕事に対するモチベーションに影響を与えます。
従業員のモチベーションが向上すれば、離職率低下や優秀な人材確保など、企業にとってのメリットも大きいです。そういった意味でも、エンパワーメントを導入し、積極的に従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出そうとする企業は多くなっています。
エンパワーメントのデメリット
メリットが多いように感じるエンパワーメントですが、導入の仕方やサポートがうまくいかないと失敗に終わってしまう可能性もあります。せっかく従業員の能力を引き出し、企業成長につなげられる力も、エンパワーメントがうまくいかなくては意味がありません。
以下では、エンパワーメントのデメリットを紹介します。デメリットを理解し、エンパワーメントが企業にとって悪影響を与えるものにならないよう、十分に注意した対策をしましょう。
ミスやトラブルが増加する可能性がある
エンパワーメントだからといって、部下に権限を与えきりだとミスやトラブルが発生する可能性があります。
これまで、上司の指示に従って業務を遂行してきた部下は、自らの意思決定や判断で業務をした経験がないです。部下にすべてを任せてしまっては、部下が困難な課題に直面した際、間違った判断をしてしまいかねません。その結果、重大なトラブルに発生してしまう可能性も。
エンパワーメントは、部下に権限を与えるだけでなく、上司のしっかりとしたサポートが必須です。権限委譲とサポートをセットにして、エンパワーメントを導入しましょう。
組織が連動しなくなる可能性がある
エンパワーメント導入によって、従業員一人ひとりの基準で意思決定を行ってしまえば、さまざまな障害が発生してしまいます。
仮に、それぞれの判断で意思決定や業務遂行すれば、お客さまへの対応に違いがでてしまうでしょう。その結果、お客さまには不信感や不満を抱かれ、企業全体の信頼を失いかねません。
また、会社の方針に沿って行動する部署と、そうでない部署が出てしまうと、会社に所属している目的や会社が目指すものは不明瞭になってしまいます。
対策としては、会社が最も大切にする理念や行動指針を軸にすることが重要です。軸とする考え方があった上でエンパワーメントを導入すれば、従業員が何か迷ったときの示しにもなります。
理念や行動指針はただ掲げているだけでは意味がありません。従業員が理解し、行動に移せるよう、浸透するような施策を積極的に計画してみましょう。
社員の負荷になる可能性がある
自分で意思決定することや、自分で仕事を進めることが得意な人ばかりではありません。中には、自分で判断できるほどのレベルに達していない従業員もいるでしょう。
上記のような従業員に対して必要以上に権限を委ねた場合、かえって逆効果になる可能性が高いです。従業員が精神的に大きなプレッシャーを感じてしまったり、業務過多で生産性低下につながる恐れがあります。
本来であれば、エンパワーメントは業務効率向上に効果的であるにもかかわらず、その逆の辞退が発生してしまう可能性がある点に注意しましょう。
エンパワーメントを高める・引き出す方法
エンパワーメントの意味やメリット・デメリットがを理解できたと思います。次は実際にエンパワーメントを導入した際、どのように従業員一人ひとりの能力を引き出し高めるのか、その方法について解説します。
エンパワーメントを高めるには2つの考え方があります。考え方を理解せず、ただエンパワーメントを導入しただけでは意味がありません。エンパワーメント本来のメリットを発揮するために、以下を参考に実践してみましょう。
構造的アプローチ
構造的アプローチとは、相対的にパワーを持つ人が、パワーを持たない相手に対して「パワー」を与えることです。その結果、組織の活性化やパフォーマンス向上・最大化を目指す目的があります。
構造的アプローチは、経営者や管理者が現場の従業員に権限を委譲したり、重要な意思決定を任せるなどの方法で実践されます。一般従業員や部署にパワーを与えることで、自らが主体的になり課題解決をしながら力を伸ばしていくことが期待できるものです。
構造的アプローチでは、権限を受けた側である従業員たちに対するサポートが重要といわれています。事前に経営方針や企業理念などをしっかり伝えた上で、1on1などをとおしてサポートしていきましょう。エンパワーメントを高めることができるはずです。
心理的アプローチ
心理的アプローチとは、従業員が持っている意欲やエネルギーを高めていくためのアプローチを言います。具体的には「自分がうまくできると思っている」いわゆる自己効力感を高めることです。個人の心理的な面に着目しながら、一人ひとりのパフォーマンス向上を目指していきます。
自己効力感を高めるためには、成功体験が重要です。ビジネスにおいては、プレゼンテーションや承認を取るなどの経験が考えられます。
従業員の内面から湧き上がる仕事に対する熱意を促す「内発的動機付け」も、自己効力感同様に重要です。ただし、内発的動機付けは人によって異なります。責任感が要因となる場合もあれば、裁量や昇格が動機付けになるケースなどさまざまです。従業員一人ひとりに合った動機付けで、仕事に対する意欲を高めてもらうようアプローチすることが求められます。
また、心理的アプローチに欠かせないのが、コミュニケーションです。上司と部下のコミュニケーションを大切に、適切なフィードバックや称賛などで部下のモチベーションを図りましょう。
エンパワーメントの導入手順
エンパワーメントは正しく導入しないと効果を発揮しません。また、導入後トラブルが発生する可能性もあります。
以下ではエンパワーメント導入手順について解説するので、これからエンパワーメントを導入予定の方は参考にしてみましょう。
①推進の宣言と企業風土の構築
まずは、組織全体にエンパワーメント導入宣言をしましょう。その際、ただ情報を伝えるのではなく、「どのような組織にしたい」という明確な目標を熱く語ることが重要です。その目標に対し、組織が大切にする価値観や目指す風土を示すことで、より具体化されます。
ただ、「エンパワーメント導入します」だけでは、従業員にとって目指すものもメリットも理解されません。メリットが理解できないまま、エンパワーメントが導入されても、従業員は興味を持てないでしょう。
エンパワーメントの効果を発揮するためには、事前準備として組織全体の共通認識を合わせておくことが重要です。ここは時間を惜しまず、しっかりと準備しましょう。最初の準備が今後のエンパワーメントの効果を左右する最も重要な部分です。
②実施する目標・ゴールの明確化をする
組織全体へのエンパワーメント導入宣言ができたならば、エンパワーメント導入に関する具体的な目標を設定しましょう。その際、従業員が感じている不安や疑問を解消するためのディスカッションなどの場を設けるのがオススメです。
ディスカッションに従業員が参加することで、不安解消だけでなく「自分の意見も反映される」という責任感を感じることができます。責任感を感じたことをきかっけに、主体的に動けるようになるという効果があるので、経営層だけでなく従業員も積極的に巻き込みましょう。
③情報共有を行う
エンパワーメントにおいて、権限委譲や意思決定は部下に託されます。その際、部下が組織の情報を理解していなくては正しい決断ができないです。そこで、エンパワーメント導入時には、組織は適切な範囲内での情報公開が求められます。
情報公開には、経営層だけが認知していた重要な情報も求められるケースも少なくありません。また、機密情報など慎重に扱うべき情報も多いです。これらの情報を従業員に開示する際は、セキュリティの強化・情報漏洩防止対策を行いましょう。
従業員に対しては、情報取り扱い方法について指導することがオススメです。
④徐々に権限を委譲する
情報効果が済めば、いよいよ権限委譲です。上司が部下に権限委譲をする際は、少しずつ実践してみましょう。
最初からすべての権限を委譲してしまうと、従業員が戸惑ってしまいます。慣れないまま権限を持ち続けると、間違った判断をしてしまう可能性も高いです。その結果、「自分には無理だ」と自信喪失してしまう従業員も少なくありません。エンパワーメント本来の効果を発揮するためには、少しずつ権限委譲することでコツをつかむ必要があります。
その際、上司は部下に対して適度なサポートをするようにしましょう。最初から丸投げではなく、部下が何か困難に直面した際は一緒に解決方法や別のアプローチを考えてください。
⑤適切な支援・フォローを行う
エンパワーメントにおいて、従業員の意思を尊重することは大切ですが、放置状態にならないようにしましょう。従業員に権限委譲したきりでフォローを怠ると、組織が目指す方向性と大きなずれが生じる可能性があります。また、いつの間にか取り返しがつかない大きなミスに発展するケースも少なくありません。
権限委譲した後は、定期的な確認を必ず実施しましょう。業務進捗の確認や、従業員の精神的・身体的な状況把握、その他にも働く環境管理なども重要です。
また、従業員が助けを求めてきたときは、適切なフォローでトラブル発展前に修正できるように対応してください。その際、上司は答えを与えるのではなく、応えになるヒントを与えることで、自ら考えて解決するという経験が従業員ができます。その結果、従業員は少しずつ成功体験を積み、成長実感を持てるようになるのです。
上司からのサポートがあってこそ、エンパワーメントは効果的に発揮されると考えておきましょう。
エンパワーメントを導入する際の注意点
適切なステップでエンパワーメントを導入することはもちろん、導入の際注意すべきことはまだまだ存在します。以下では、エンパワーメントを導入する際どのような点に注意すべきか、3つのポイントについてまとめました。エンパワーメント導入を成功させるためにも、参考にしてください。
権限委譲の範囲や判断基準を明確にする
エンパワーメントにおいて権限委譲は基本的な考えです。しかし、権限委譲と一概に言っても、その範囲や内容は人ぞれぞれ異なります。そこで、エンパワーメントを導入する際は、権限委譲の範囲を誰が聞いてもわかるよう、明確にしておきましょう。
権限委譲だから何でもやっていいと考える従業員がいると、そこから組織との大きなずれが生まれてしまいます。また、自分でやらなくてはと、自己責任の範囲まで責任を負ってしまう従業員もでてきてしまう可能性も高いです。
人材育成のためのエンパワーメントで、大きな損失や優秀な部下の挫折だけで終わってしまっては意味がありません。効果的にエンパワーメントを発揮するために、どこまでの権限を委譲し、どこからは上司の判断が必要になるか、事前に明確にしましょう。
失敗を容認する環境を作る
最初からなんでもうまくいくとは限りません。エンパワーメントも同様です。権限を委譲されてすぐに力を発揮できる従業員は少ないでしょう。
エンパワーメントを導入し、部下に権限委譲したばかりのうちは、経営層や上司が想像できなかったミスやトラブルが発生するかもしれません。しかし、部下にとっては慣れない状況の中で必死に試行錯誤して行動した結果です。上司はその結果をただ𠮟るのではなく、どう改善できるか提案や話し合いをしながらフォローしましょう。
その積み重ねが、部下にとっては「相談しやすい上司」という存在になり、双方にとって良い関係を築けます。
社員の向き不向きを見極める
すべての従業員に対し、エンパワーメントの効果が発揮されるとは限りません。人によっては、権限を委譲されることで負担を感じたり、プレッシャーから委縮してしまう可能性があります。
「指示通りに動くのは得意だけど、自分で考えるのは苦手」「計画を立て、行動することが苦手」と考えている人も多いです。また、「潜在能力は高くてもプレッシャーがかかると本領発揮できない」という人もいるでしょう。
エンパワーメントはあくまで、従業員の能力を引き出し、企業の生産性を高めるための手段の一つです。権限という責任を負うことで萎縮してしまい、パフォーマンスが低下してしまう従業員に対して、無理に権限委譲しても意味がありません。
エンパワーメントを導入する際は、スタッフの適性を見極めて実行することが重要です。
エンパワーメントの導入事例
最後に、実際にエンパワーメントを導入している企業の成功例を紹介します。エンパワーメントの導入がうまくいっている企業を参考にすれば、はじめてのエンパワーメント導入でも成功イメージが持てるはずです。
これからエンパワーメント導入を考えている企業の方は、以下で紹介されている3社を参考に、自社に合う方法や運用の仕方を考えてみましょう。
星野リゾート
星野リゾート(株式会社星野リゾート)は旅館やホテルを主軸に全国展開している企業です。
ハードな仕事内容である宿泊業界のため、星野リゾートでは退職率の増加を課題としていました。そこで、星野リゾートでは退職する社員にインタビューを実施し、トップダウン方式のマネジメントに問題があったことが判明したため、エンパワーメントの推進が開始されたのです。
具体的には、従業員に対して適切な情報発信を行い、自由に発言できる機会を提供しました。さらに、従業員に権限委譲することで、仕事に対するモチベーションを保ちながら働ける環境づくりに取り組み、離職率低下を実現させたのです。
スターバックスコーヒージャパン
世界中で人気が高いコーヒーショップ「スターバックスジャパン」では、エンパワーメントの一環として接客に関するマニュアルが用意されていないです。
「お客さまが何をしてほしいか考えてサービスを提供しよう」という内容だけがあり、従業員自らが考えて接客することを促しています。結果、お客さま目線のサービスが実践できる従業員が増え、顧客満足度向上を実現させました。
ザ・リッツ・カールトン
有名ホテルであるリッツカールトンでは、3つのエンパワーメントを定めていることで知られています。「上司の判断を仰がずに自分の判断で行動できること」「自分の通常業務を離れて、セクションの壁を超えて仕事を手伝えること」「1日2000ドルまでの決裁権」です。
ザ・リッツ・カールトンで定めているエンパワーメントは、すべてがお客さまにとって満足度が高いサービスを提供することが目的となっています。お客さまの要望やニーズに対して迅速に応えるためのコミュニケーションやサービスを実現するために、社内ではさまざまな情報共有が日々行われているそうです。
エンパワーメントでは従業員・企業がともに成長できる
変化が激しく、人材不足が課題視されているからこそ、従業員一人ひとりの潜在能力を引き出すエンパワーメントは重要です。ビジネスだけでなく、介護や医療、教育現場などさまざまな分野でエンパワーメントは今後も注目されていくでしょう。
エンパワーメントは、正しいステップで導入すれば効果を発揮します。しかし、権限委譲をしすぎたり、従業員にプレッシャーを感じさせてしまえば逆効果になる可能性も高いです。
もし、エンパワーメント導入を悩んでいる企業の方は、まずは、既存の従業員にインタビューし、現状を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。今まで気づけなかった課題が見えてくるかもしれません。
従業員の効果が最大に発揮されれば、企業成長にもつながります。時間はかかりますが、焦らずに丁寧なエンパワーメント導入で、高い目標を目指してみましょう。
用語集の記事
ビジネス用語の関連記事
敬語の関連記事
敬語の意味の関連記事
時候の挨拶の関連記事
漢字の読み方の関連記事
[PR]"好条件"の管理部門転職なら
管理部門・バックオフィスで転職するならSYNCA(シンカ)。
経理、総務、法務、労務、情シスなどの職種や細やかなスキル設定により 採用企業から一人ひとりに合ったスカウト求人が直接届きます。
まずはスキルに応じたあなたの適切な年収を無料で診断しましょう。