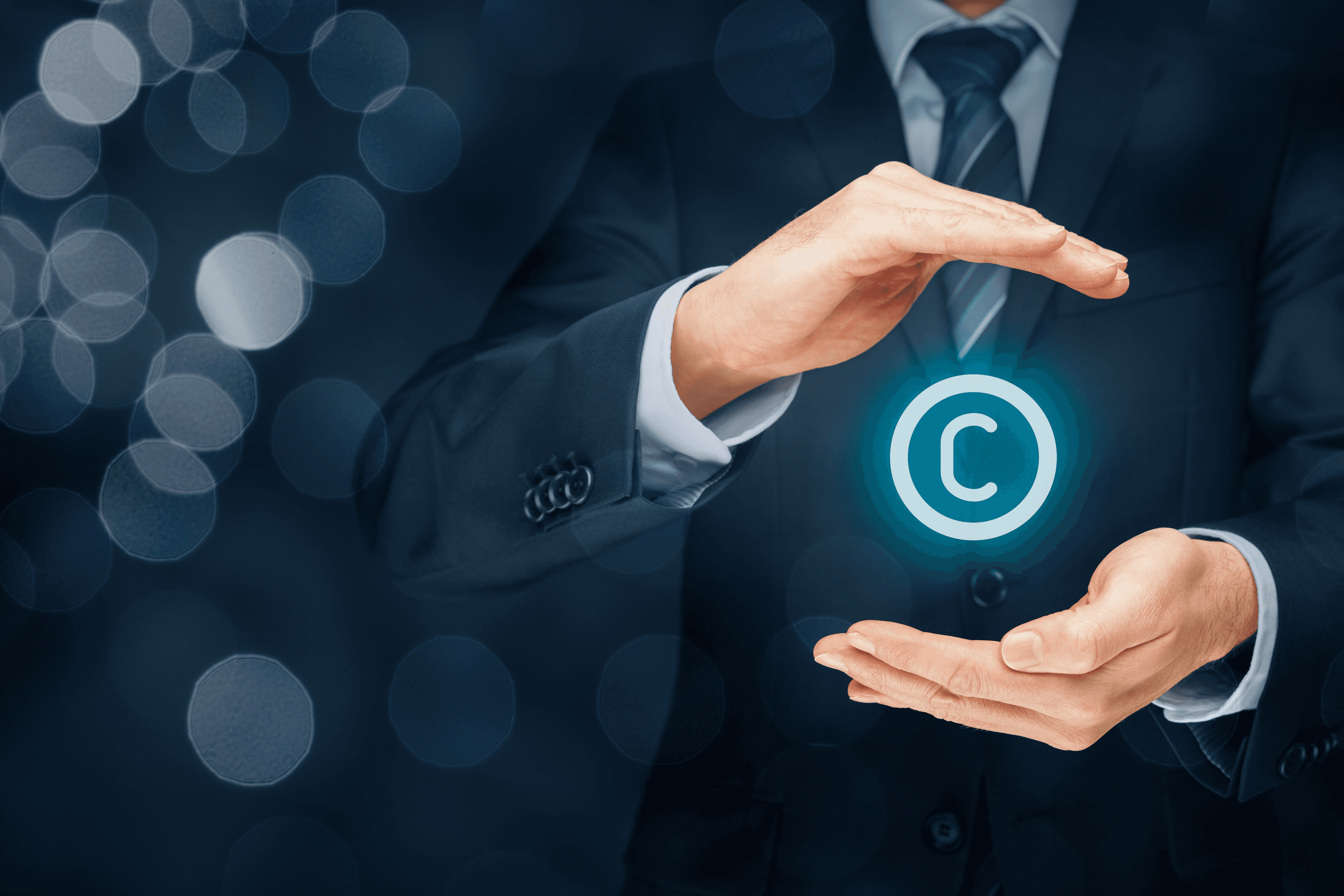目次
コンテンツビジネスや地域創生ブランド・特許の国際出願などが拡大する現在、弁理士が活躍できるフィールドは広まっています。このようななか、弁理士の具体的な仕事や、資格取得は難しいのかが気になる方も多いのではないでしょうか。 この記事では、弁理士の仕事内容や資格試験の概要、資格をどのような仕事で活かせるかなどについて、知的財産管理技能士と比較しながらまとめました。弁理士資格の取得に関心のある方はぜひお読みください。
※時間がない方へ・・記事を読む時間が無い方でバックオフィス系の転職を検討中の方は、まずは「WARCエージェント」に無料登録してみましょう!
弁理士とはどんな仕事?
弁理士は知的財産権の取得や知的財産の紛争解決を業務として行うことができる職業であり、資格です。「知的財産(知財)」とは、人間の知的・精神的な活動から生まれるアイディアや創作物で、かつ財産的価値のあるもののことを言います。よりわかりやすく言い換えるなら、特定の者に独占させる価値のある情報のことです。具体的には発明や音楽、営業秘密などが知的財産に当たります。
弁理士を名乗るためには、弁理士の試験に合格して資格を取得しなくてはなりません。弁理士資格は知財関連の最高峰の国家資格です。弁理士の資格を取得することは、知的財産に関する業務を行うために必要な学識や応用能力を有することの証明となります。
知的財産管理技能士との違い
知的財産管理に関係する資格に「知的財産管理技能士」という資格もありますが、それぞれ違いがあります。
弁理士は主に知的財産権を新たに入手する業務を行いますが、知的財産管理技能士はすでにある知的財産権を活用する役割を担います。弁理士は知的財産の申請などを行うことができるのに対して、知的財産管理技能士は知的財産を管理(活用・利益化)することに役立つ資格です。
以下、両者の違いを表にまとめます。
| 弁理士 | |
|---|---|---|
試験の目的 | 知的財産を管理する技能の習得レベルの測定・評価 | 弁理士として必要な学識及びその応用能力を有するかどうかの判定 |
認定期間 | 期限なし | 期限なし※ |
業務独占 | なし | あり※:特許、実用新案等に関する特許庁に対する申請代行業務 |
名称独占 | あり | あり※ |
企業との関係性 | 情報・通信、コンテンツ業界、金融業などで知財の社内担当になる | 特許事務所に勤務して企業から委託を受ける、製造業などの企業の知財部や法務部に勤務する |
※弁理士は認定の期限はありませんが、5年間で70単位(1単位1時間)以上の研修を受講することが義務付けられています。
※弁理士だけに許された業務独占は上記の通りですが、弁理士と弁護士にのみ許される業務もあります。
※「弁理士」を名乗るには、試験に合格するだけでなく日本弁理士会に登録することも必要です。
弁理士の主な仕事内容
弁理士の主な働き方としては、特許事務所に所属したり企業内弁理士として勤務したりするほか、独立開業するといった選択肢があります。
弁理士の主な仕事内容について解説します。主な仕事は次の通りです。
【弁理士の主な仕事内容】
- 知的財産関連の取得手続き
- 知的財産関連のトラブル解決
- 取引関連業務・コンサルティング業務
すでに軽く述べた通り、主となる業務は知的財産権を取得するための業務です。取得に関連する業務と、取得している権利を守る業務が弁理士の仕事だと言うことができます。
それでは、弁理士の主な仕事内容について1つずつ見ていきましょう。
知的財産関連の取得手続き
まず主たる業務として、特許・意匠・商標・実用新案などを権利化するという知的財産関連の取得手続きがあります。申請された知的財産を客観的に評価し、特許庁に対して申請を行います。
具体的には、依頼主のアイディアやデザイン・ロゴマークなどを権利化するために、先行案件の調査を行う、特許庁に提出する書類を作る、申請が拒絶された時のフォローを行うなどが挙げられます。
一般的に言うと、アイディアは特許や実用新案に、デザインやロゴマークは意匠に、言葉を使う社名や商品名は商標に当たります。
知的財産関連のトラブル解決
知的財産関連のトラブル解決も業務の1つです。申請・登録済みの知的財産を意図的あるいは悪意なく使用してしまっており、権利を侵害しているというケースもあります。そういったケースへの対応を行います。
自社の製品が他社の知的財産を侵害していると警告を受けた、他社の製品が自社の知的財産を侵害していたといった場合の対応方法のアドバイスを行います。訴訟に発展した場合には代理人として裁判所での手続を行うこともあります。
取引関連業務・コンサルティング業務
知的財産に関する相談への対応やコンサルティングとして、弁理士は法律や実例に基づいたアドバイスを行います。主な依頼・相談の内容は、自社で開発した技術を権利化したい、利用しようとしているデザインに問題がないか確認したいなどといったことが挙げられます。
弁理士のメインとなる業務は知的財産権の取得に関するものですが、コンサルティングはその前の段階に当たる業務です。権利取得の代行案件を得るためにも、コンサルティングは重要な業務だと言えます。
弁理士資格の概要
弁理士の資格試験は3段階に分かれており、それぞれ年に1回ずつ行われます。チャンスは年に1回ということになります。3つの段階とは、短答式筆記試験・論文式筆記試験・口述試験です。
それぞれの試験方式は、五肢択一マークシート(短答式)・記述式論文(論文)・口頭試問(口述試験)となっています。なお論文は必須科目・選択科目に分かれており、日程も別となっています。口述試験は知識についての内容であり面接ではありませんが、コミュニケーションや態度も見られているものと思いましょう。
受験料は12,000円で、「特許印紙」で支払います。「収入印紙」は不可なので混同しないように注意しましょう。
以下に、試験日程・受験資格・難易度・試験科目・勉強方法について解説します。
2023年弁理士資格の試験日程
弁理士試験は例年、短答式が5月・論文式が6月下旬~7月上旬・口述が10月に行われます。2023年の日程は以下の通りです。
■2023年弁理士資格の試験日程
- 短答式筆記試験:5月21日(日)
- 論文式筆記試験:7月2日(日)(必須科目)/7月23日(日)(選択科目)
- 口述試験:10月21日(土)~23日(月)のうち1日
試験日程とともに、申し込みの受付期限やそれぞれの合格発表の期日にも注意してください。参考までに、受付期限と合格発表の期日は以下の通りです。
■2023年弁理士資格の申込期間・合格発表期日
短答式申込期間:3月15日(水) ~4月5日(水)
短答式合格発表日:6月12日(月)論文式合格発表日:9月25日(月)口述試験合格発表日:11月9日(木)申し込みの受付期間はもちろんですが、合格発表を見逃してしまっていると、次の試験の準備に差し障りが出るほか、場合によっては受験忘れも起こりかねません。日程はあらかじめ確認しておきましょう。 受験資格 弁理士試験の受験資格は次の通りです。■弁理士資格の受験資格短答式筆記試験:なし 学歴、年齢、国籍等による制限は一切なし論文式筆記試験:短答式試験に合格した者口述試験:論文式試験に合格した者短答式、論文式、口述、と順に合格していかなければなりません。ただし免除制度があり、短答式と論文式は一度合格すると翌年・翌々年の2年間は有効で、再受験する際に免除となります。そのほかやや複雑ですが、免除の規定が複数あります。学歴(取得単位)・職歴や過去の合格歴などを確認しておきましょう。なお免除期間が設定されている条件もあります。期限が切れていないかも含めてよく確認しておくことが必要です。 弁理士資格の難易度 弁理士資格の難易度について、類似の資格などと比較してみましょう。類似の内容の知的財産管理技能検定のほか、難易度でよく比較される公認会計士・税理士・医師・弁護士などと比較しました。
資格の種類 | 合格率 | 勉強時間 |
|---|---|---|
弁理士 | 6~8% | 3,000時間 |
知的財産管理技能検定2級 | 40% | 50時間 |
知的財産管理技能検定1級 | 2~8% | 400時間 |
公認会計士 | 10% | 4,000時間 |
宅建士 | 15~18% | 300~500時間 |
税理士 | 15~20% | 3,000~4,000時間 |
医師免許 | 90% | 5,000時間 |
弁護士 | 30~40% | 3,000~8,000時間 |
合格率が低いほど難易度が高いとは単純に言い切れないものではありますが、合格率・勉強時間ともに難関資格として知られる税理士や公認会計士などと同じ程度に難易度が高いことがわかります。弁理士は理系出身者が取得するケースが多い資格でもあり、「理系の弁護士」とも呼ばれています。
試験科目・出題数
試験科目と出題数については試験範囲が広いのが特徴です。合格率が低いことからもわかるように、簡単な試験ではありません。試験科目と出題数については以下の通りです。なお合格者を文系・理系で比較すると、理系学部出身者が7~8割を占めています。新しい技術を扱うことも多いため理系の知識があると有利です。
【短答式試験(全60問・マークシート・3.5時間)】
特許・実用新案に関する法令:20題意匠に関する法令:10題商標に関する法令:10題工業所有権に関する条約:10題著作権法及び不正競争防止法:10題短答式試験の合格基準は60点満点の65%(39点)です。各科目の最低基準は満点の40%となっており、合格率は10%前後です。1科目でも基準を下回ると不合格となります。
【論文式試験】
必須科目:特許法・実用新案法(2問)、意匠法(1問)、商標法(1問)選択科目:理工Ⅰ(機械・応用力学)、理工Ⅱ(数学・物理)、理工Ⅲ(化学)、理工Ⅳ(生物)、理工Ⅴ(情報)、法律から1科目(1問)必須科目の合格基準は、標準偏差による調整後得点の平均が54点以上かつ47点未満の得点の科目が1つもないことです。選択科目の合格基準は満点の60%以上となっています。合格率は20%台を推移しています。
【口述試験(各科目10分)】
- 特許・実用新案に関する法令
- 意匠に関する法令
- 商標に関する法令
口述試験の合格基準は、採点基準をABCのゾーン方式として「答えが不十分である場合」のC評価が2科目以上ないことです。合格率は例年90%を超えています。勉強方法
弁理士試験合格のための勉強時間の目安は3,000時間と言われています。働きながら勉強して取得を目指した場合、どのぐらいの年月が必要となるのでしょうか。平日に3時間、休日に8時間勉強したとして、年間休日110日とすると1年の合計勉強時間は1,645時間となり、2年弱かかる計算となります。
ただし通信講座などは1年のコースが主流で、専門学校に通う人も多くいます。社会人も通いやすい時間帯のコースもあります。そのほか、独学で合格する人もいます。
方針としては、まずは短答式の合格を目指しましょう。短答式の試験に合格しなくては次に進めません。とくに、論文試験とも重なる特許法・実用新案法・意匠法・商標法からメインに勉強しましょう。なお試験は過去に出題されたことのある問題や類題が多いため、過去問を解くのは必須です。過去問を解きながら知識を身に付けていく方法と、一通りインプットしてから過去問を解く方法とがあります。 弁理士の資格を取得するメリット 弁理士の資格を取得するメリットには、次の点が挙げられます。
【弁理士の資格を取得するメリット】
高収入を目指せるキャリアの幅が広がる大学などの研究機関知的財産経営コンサル難関資格だけあり、合格すると高い収入を得ることが期待できます。そのほかキャリア面でも幅広く活躍できる可能性が高まります。とくに近年は、海外特許やコンテンツビジネスの伸長などがその可能性を後押ししています。確かに、AIに取って代わられる可能性が示唆されるなど将来性を不安視する向きもあります。しかしプラスに働くと考えられる要因もまだまだ存在しています。では次に、とくに収入面とキャリア面のメリットについて解説します。 高収入を目指せる 弁理士の年収の相場は700~750万円とよく言われます。厚生労働省による「令和3年度 賃金構造基本統計調査」では945万円となっています。「令和3年度 賃金構造基本統計調査」 サラリーマンの平均年収は一般に450万円弱とされているので、弁理士の年収は高いと言えます。弁理士として年収アップするためには、安定した事務所に就職・転職することが手っ取り早い方法です。安定した事務所は案件が多いほか、さまざまな業界で重宝されるため案件の幅も広い傾向があります。スキルを高めることもできます。さらに海外での特許取得サポートは単価が高いため、英語を使うような外国出願を扱うのも年収アップにつながります。とくに近年は国でも国際競争力を高めるために知的財産の活用を推進しており、外国出願の必要性が高まっています。
弁理士として高収入を目指すならならSYNCAがおすすめ
弁理士としてよりよい条件の転職を考えているなら、転職サイトのSYNCAがおすすめです。SYNCAは事務系・バックオフィス系の求人に特化した転職サイトです。特許事務所や知財部のあるメーカーはもちろん、IT・インターネット系やエンタメ・デザイン系など、独自のノウハウや技術を持つ企業の求人が数多く掲載されています。まずは以下のリンクから求人をチェックしてみてください。
掲載案件が多いため、より希望に近い条件の転職先を探しやすくなっています。
キャリアの幅が広がる
弁理士の資格を取得すると、キャリアの幅を広げることができます。特許事務所や企業の知財部などで働くほか、経験を積んで独立を目指すことも可能です。
また世界的に弁理士に対するニーズが高まっているため、いろいろな業界で需要があります。とくに独自の技術やサービスを保有しているベンチャーやスタートアップ企業が多いほか、コンテンツビジネスや企業のブランディングといった面からのニーズもあります。将来的に知的財産がビジネスと結び付く可能性が高いと言えます。
まとめ
弁理士は知的財産の手続などを独占的に行うことができる国家資格です。試験科目が多く合格率も低い最難関の資格の1つですが、3段階の試験は1度合格すると免除される期間もあるので、1つずつ合格していくことも可能です。
特許事務所や企業の知財部のほか、実績を積んで独立することも選択肢の1つとすることができます。いずれにせよ、まずは資格を活かせる事務所や企業に転職するのが一般的です。弁理士として転職する際は、SYNCAをご活用ください。
法務に関する記事一覧
臨床法務とは |
[PR]"好条件"の管理部門転職なら
管理部門・バックオフィスで転職するならSYNCA(シンカ)。
経理、総務、法務、労務、情シスなどの職種や細やかなスキル設定により 採用企業から一人ひとりに合ったスカウト求人が直接届きます。
まずはスキルに応じたあなたの適切な年収を無料で診断しましょう。