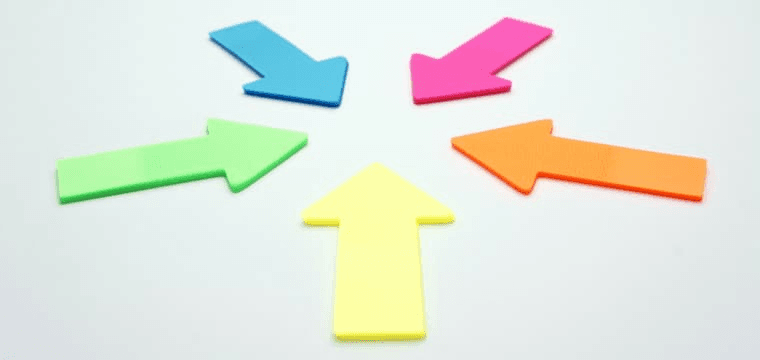目次
シェアードサービスとは、企業改革を目的とした手段の一つです。複数の事業部やグループ企業で構成された組織が、間接部門の業務を一か所に集約することで、グループ経営を円滑に進めることが期待されています。最近では、大企業がシェアードサービスを利用する機会が増えており、再注目されているのです。
そこで、今回は今注目が集まっているシェアードサービスについて解説をします。「シェアードサービスって何?」「利用メリットは?」など、シェアードサービスについて疑問を抱えている方にも、理解いただける記事です。本記事を最後まで読んで、シェアードサービスについて理解を深めてみましょう。
※時間がない方へ・・記事を読む時間が無い方でバックオフィス系の転職を検討中の方は、まずは「WARCエージェント」に無料登録してみましょう!
シェアードサービスとは
シェアードサービスとは、複数のグループ企業からなる企業が、コーポレート業務を一か所に集約させる企業改革のことをいいます。ここでいう「コーポレート業務」には、以下の業務が含まれます。
- 経理
- 財務
- 総務
- 法務
- 人事
- 情報システム
- 監査
これらの業務は、どの企業でも基本的な業務内容に大きな違いはありません。そのため、業務プロセスやシステムを標準化し一か所に集約することで、企業全体のコスト削減を図れるのです。
シェアードサービスの導入の目的
シェアードサービスの最大の目的は、経営の強化です。グループ企業各社で共通する間接業務をシェアードサービスに集約すると、以下のような効果があるといわれています。
- 業務の効率化
- 標準化した業務知識を蓄積
- グループ企業の運用
また、人事や設備コストを削減できるため、導入・運用に成功すれば、高い費用効果をもたらします。
ただし、これまでの習慣から変化するため、強いリーダーシップのもと、企業全体で改革を進める力強さが必要です。
シェアードサービスとBPOとの違い
シェアードサービスと似た言葉で使われるのが「BPO」です。BPOは、Business Process Outsourcingの略称で、企業の業務プロセスを一括して外部に委託する業務形態のことをいいます。
サービスの種類 | 内容 | 委託先 | 主な目的 |
|---|---|---|---|
シェアードサービス | グループ企業内の間接業務を社内で一か所に集約させる | 企業内 | 業務効率化・コスト削減 |
BPO | 企業の業務プロセスを一括して外部に委託する | 外部企業 | 業務効率化・コスト削減 |
上記のとおり、シェアードサービスもBPOも主な目的は、業務効率化とコスト削減で同じです。しかし、シェアードサービスは社内の一か所に集約させることに対し、BPOは外部委託する点が異なります。
シェアードサービスが再注目されている背景
シェアードサービスが注目されている背景には、3つの要因があります。
①少子高齢化による人手不足問題
企業の労働不足が深刻化する中で、いかに効率的に働くかが重要になりました。シェアードサービスは、小人数で管理・間接業務を任せられるため、少ない労働力でも業務を実行できます。その結果、企業の人材不足解消・人材コスト削減につながるのです。
②働き改革への対応
働き方改革により企業には労働時間の短縮や柔軟な働き方が求められるようになりました。シェアードサービスは、業務改革をとおして作業時間の短縮を実現できます。長時間労働における従業員のストレスや業務負担を軽減できるため、生産性向上につながるとされています。
③業務効率アップ
昨今RPAやAIなど、IT技術を活用した業務効率化が注目されています。これらを導入する方法として、シェアードサービスが注目されるようになりました。シェアードサービスで業務を集約することで、技術導入の効果を最大限に引き出すことができます。その結果、アウトソース業務の内製化実現が可能です。
上記のような背景で、シェアードサービスは再注目されるようになったといえるでしょう。
シェアードサービスの運用する際の組織形態
シェアードサービスの導入時に検討しなくてはいけない要因に、担当部署を本社配下にするか、子会社として独立させるかという点があります。
以下では、それぞれの特徴を解説します。どちらにも良し悪しがあるので、慎重に検討してください。
子会社化
シェアードサービスを独立させるメリットは、別法人になるため、シェアードサービスそのものの売上やコストが明確に管理しやすくなる点です。独立した企業として利益獲得を目指すために、シェアードサービス自体の業績を評価できるようになります。
しかし、子会社化には大規模な組織変更が伴います。組織やシステムを一から構築できる反面、システムやデータの統合に初期費用が掛かるだけでなく、現場の混乱を招く危険性があります。
シェアードサービスの導入に際し、子会社化することには長期的な計画と今期強く進める心構えが重要でしょう。
本社に配置
シェアードサービスを本社に置くメリットは、サービス導入のしやすさがあげられます。各部門から一部業務を切り離す形で実施するため、大規模な組織変更は必要ありません。そのため、子会社化に比べ従業員の混乱を招かずに実行できます。
ただし、従業員の業務プロセスやシステムをそのまま引き継いでしまうと、シェアードサービス導入効果が出にくいです。業務工数削減やシステムの課題解決を目的にしても、従来のやり方に囚われすぎてしまう可能性があります。
組織改革のためには、多少の変化は必要なため、期待する効果や導入の目的をはっきりさせた上で、運用方法を決めましょう。
シェアードサービスのメリット
シェアードサービスを導入するメリットは、主に4つあります。以下では4つのメリットについて一つずつ解説をするので、導入を検討している方は参考にしてください。
コスト削減につながる
シェアードサービスでは、間接部門の業務を一つに集約できるため、各事業所で発生していた手間や負担を削減できます。また、独自管理の設備をまとめることができるため、管理費の削減、さらに人件費の削減も期待できます。
シェアードサービスの導入で、業務の効率化と標準化が実現できれば、作業工程の無駄を省けるようになります。その結果、従業員が感じていた無駄な業務へのストレスや負担を削減することも可能です。
とくに、大企業だと、企業規模が大きくなるにつれて重複する業務が増えます。しかしシェアードサービスを導入すれば、それらの業務を一元化できるため大幅なコスト削減につながるでしょう。
業務の効率化と品質の向上
シェアードサービスを導入すれば、これまで各事業所で管理していた知識や技術を一つに集約することが可能です。
それぞれで得た情報を共有できれば、業務効率が上がるだけでなく、専門性も高まります。また、業務の精度が高まり、品質向上につながるでしょう。
間接部門が一元化されれば、営業やマーケティングなど直接部門へ注力しやすくなります。その結果、企業全体の経営力向上も期待できるでしょう。
企業全体の管理体制の強化
これまで、各事業所で管理されていた情報を、シェアードサービスを導入すれば一つに集約できます。情報が集約すれば、各事業所の状況確認への時間や手間を削減可能です。
また、情報を一つに集約することで、スムーズに情報共有・浸透ができ、企業全体の管理体制を強化できるでしょう。
集約すれば、不正も起こりにくくなり、健全な企業経営にもつながります。その結果、企業の社会的信頼や企業価値が上昇し、企業成長の勢いが期待できるでしょう。
人材の有効活用
社内の余剰人員を有効に活用できるのも、シェアードサービスのメリットです。
これまで点在していた間接部門の業務を一つに集約すれば、人材共有も可能になります。労働人材不足が課題視される現在、シェアードサービス導入を機に少人数での対応が可能になれば、課題解決につながるでしょう。
これまで間接部門を担っていた人材は、別部門への異動を促すことで、注力したい部署の人材補填にもつながります。
シェアードサービスのデメリット
次は、シェアードサービスを導入するデメリットについて解説をします。デメリットを理解し、シェアードサービス活用時に注意してください。
導入にコストが発生する
シェアードサービスを活用する際は、従来のシステムや運用方法を見直す必要があります。見直しの際は、各事業所で担っていた業務の洗い出し、業務の運用方法など、あらゆる工程の確認が必要です。そのため、間接部門を一元化するまでに時間と労力がかかるでしょう。
また、新たなシステムを活用する際は、新システム導入のコストが発生します。ただし、長期的に考えると、シェアードサービスを導入することで、人件費削減や経営力の向上などメリットは豊富です。
目先のコストだけに捕われて導入を懸念するのではなく、長期的に考えながら検討してみましょう。
イレギュラー対応の難しさ
シェアードサービスを一元化することで、専門知識が一か所に集約されます。情報共有をしやすく、専門性が高くなることにメリットを感じますが、担当者不在の場合対応できる人材がいないというデメリットもあります。
間接部門の業務は、企業利益に直接関係することは少ないです。しかし、突発的なトラブル発生時に速やかな対処ができないと大きなトラブルにつながりかねません。
いざというときに、トラブル対応ができる人材を事前に準備しておくようにしてください。シェアードサービスと会社をつなぐ窓口の担当者を1人配置しておくだけでも効果はあるでしょう。
モチベーションの低下の懸念
シェアードサービスで行う仕事は、ルーティン化しやすい業務です。そのため、単調作業になれた従業員のモチベーションが維持できない可能性があります。
また、直接業務と比べるとキャリアパスをイメージしにくい間接部門には、異動を好まない従業員も少なくありません。
一見地味に見える間接業務ですが、企業経営の土台を支える重要な役割があります。企業は、この重要性をしっかり従業員に伝え、意欲的に業務に取り組めるような体制を整えるようにしてください。
シェアードサービスの対象業務
シェアードサービスの対象になるのは、ルーティン業務です。共通性が高く、日常的に実施するルーティン業務は、シェアードサービスに最適です。
一方で、専門性が高い業務は、スキルと専門知識が必要になるため、シェアードサービスには向いていません。
ルーティン業務 | 一般会計 |
債務管理 | |
給与・賞与計算 | |
福利厚生 | |
社会保険 | |
メール管理 | |
備品管理 | |
IT業務 など | |
専門性の高い業務 | 管理会計 |
資金調達 | |
内部監査 | |
人事制度構築・運営 など |
人事労務業務
人事労務は、ルーティン業務が多いため、専門性を除いた業務以外をシェアードサービスの対象にしやすいです。具体的には、給与・賞与計算、社会保険の手続きや福利厚生の受付が考えられます。
一方で、人事制度の構築や運用、採用業務全般は、専門性が必須のため、シェアードサービスには向いておらず、導入率は低いです。
経理財務
経理は、間接部門業務の中で最もシェアードサービスに適しているといえるでしょう。
経理や財務は、ルーティン業務が多いです。シェアードサービスを導入する企業のほとんどが、一般会計や債務管理の支払・入金業務をシェアードサービスに移行しています。
ただし、管理会計や内部監査など、専門性を持った人的確認が必要な業務は、導入に向いていないです。向き不向きを判断した上で、導入してください。
総務業務
総務の業務にも、多くの企業がシェアードサービスを導入しています。
具体的には、メール・社内便業務、設備管理や資産管理などです。その他にも、オフィス・施設管理、文房具・備品管理など、業務に必要な備品関係の管理については、シェアードサービスに移行しやすいでしょう。
IT業務
IT業務もシェアードサービスの対象になりやすいです。
中でも、ハードウェア・ソフトウェアの管理・サポート業務や、アプリケーション開発・保守・運用などを対象にする企業は増えています。また、お客様や社内からIT関連の問い合わせに対応するヘルプデスク業務も、シェアードサービスを導入しやすいでしょう。
IT業務は今後ますます増えていくことが予測できるため、シェアードサービスを導入し効率的に運用することが望ましいです。
シェアードサービス導入のポイント
シェアードサービスを導入する際は、従業員や現場に混乱が起こらないよう、注意しながら導入しましょう。以下では、導入時に気を付けるポイントを解説します。これから導入予定の方は、参考にしてください。
課題を把握する
そもそもなぜシェアードサービスを導入すべきか、組織の課題を把握することから始めてください。
- どのようなシステムで業務を行っているか
- 繁忙期はいつか
- 誰が、どのくらい、その作業に時間をかけているか
- 業務課題は何か
上記のように、組織の現状を整理して考えると、課題を把握しやすいです。
これらの分析を実施する過程で、本質的な課題を洗い出し、シェアードサービス導入による効果や事業成果を実感しやすくなります。
また、シェアードサービスではなく、BPOやその他の手段の方がいいという判断になる可能性も出てきます。
社内課題解決のためには、課題に合った手段を導入すべきです。そのためにも、現状把握は必ず実施してください。
導入する部門を選定
組織の課題が把握できたら、シェアードサービス導入部署を選定しましょう。基本的には、間接部門を一か所に集約することになりますが、中には集約できない部署もあります。どの業務なら標準化できるか判断した上で、集約してください。
シェアードサービス対象になる部署は、以下のような部署です。
- 税務・経理
- 人事・総務
- 情報システム
- 物流
部署選定の際は、シェアードサービス導入済みの企業事例を参考にするのがオススメです。他社の成功事例を見て、シェアードサービス導入時のイメージを持てるでしょう。
システムやツールの見直し・統一
シェアードサービス導入前に各部署や各企業で利用されていたツールがあると思います。シェアードサービス導入時は、それらのシステムを見直す必要があります。
システムを見直す際は、事前に把握している組織課題を解決するために有効なシステムはどれかという判断で比較しましょう。そうすることで、より最適なシステムを選定できます。
システムの選定ができたら、システム担当者と調整をしながら導入を進めてください。このとき、システム担当者の混乱を招かないよう、相手への配慮を忘れないよう調整しましょう。
シェアードサービス導入の成功事例
最後は、これまで紹介してきたシェアードサービスの導入が成功している企業を5社紹介します。
シェアードサービス導入成功事例を見れば、シェアードサービスを導入した際のイメージが持てると思います。自社と同じ組織規模や課題を持っている企業を参考に、イメージを膨らませてください。
NEC
ビジネスユニットを9つ、連合秋者を46社持つNECグループでは、間接部門にある総務・人事・経理などにシェアードサービス導入しました、
上記で紹介した業務は、グループ会社各社に共通しているものでした。しかし、制度や習慣が各社異なっていたため、人員配置やオペレーションに改善の余地があったのが導入背景です。
NECグループでは、出張の改革を先行して導入を進めました。出張申請から旅券手配まで、従来であれば2〜3日かかっていたのを、出張者が自ら手配できるような仕組みへの変更です。
この結果、申請から手配まで20分程度に短縮でき、事務処理の工数も約3割削減できたという効果でました。
大和ハウス工業
大和ハウス工業では、企業成長を維持することを目的に、82の事業所で分散されていた経理業務を、シェアードサービスにて集約しました。
シェアードサービス導入以前は、各事業所が独自のプロセスで経理業務を行っていたため、ミスの多発が課題でした。そこで、印刷業務や入力業務といった、各事業所共通の業務をシェアードサービスで統一。その結果、業務効率化が進んだだけでなく、ミスの削減にもつながり、従業員の心的負担が軽減されるという効果が出ています。
この結果は、従業員のはたらき方改革にもつながる大きなメリットでした。
P&G
世界最大の消費財メーカーであるP&Gでは、1999年に経理部門を中心に80か国以上のバックオフィス業務をシェアードサービスで集約しました。
シェアードサービス導入により、10億円のコスト削減を実現。さらに、2004年には売上原価前対比3割超減に成功という、大きな効果を出しました。
サッポロ
連結経営の強化や経営資源の効率化を目的としたホールディングス化を行ったサッポロでは、シェアードサービスを導入しました。シェアードサービス導入の目的は、グループ企業に重複する間接業務の統合による効率化と事業会社組織を戦略部門に集中させることによる戦略機能の強化です。
その結果、サッポロでは業務品質の向上・効果的な人員体制・業務の進め方の見直し・インフラ整備の実現に成功しました。
LIXIL
LIXILグループとは、トステムやINAXなどが統合して誕生したグループ会社です。統合当時は、105社ほどの子会社を持ち、それぞれに間接部門が存在していました。
これらのグループ会社が一体感を作るのが目的で、LIXILグループでは会計システムの統合を実施。子会社が持つ販売や人事などの基幹システムを切り離し、会計システムのみを統合する選択をしたのです。
その結果、各子会社の基幹システムに大きな影響を与えることなく、経営部門の人材配置が可能になりました。
シェアードサービスの導入検討を
シェアードサービスの導入は、コスト削減や業務効率化だけでなく、企業全体の経営力強化にもつながります。企業全体の業務を標準化・一元化することで、品質のクオリティを担保し、お客様満足度にもつながるでしょう。
シェアードサービス導入時には、現状の課題把握やシステムの見直しなど、多少の工数はかかります。しかし、長期的にみるとコスト削減など利益につながることばかりです。
慎重に導入をし、運用に成功すれば大きなメリットが得られるでしょう。導入を検討している方は、今回紹介した内容をもとに、シェアードサービス導入を考えてみてください。
ビジネスに関する記事一覧
働き方の関連記事
給与・確定申告などの関連記事
ビジネスの関連記事
[PR]"好条件"の管理部門転職なら
管理部門・バックオフィスで転職するならSYNCA(シンカ)。
経理、総務、法務、労務、情シスなどの職種や細やかなスキル設定により 採用企業から一人ひとりに合ったスカウト求人が直接届きます。
まずはスキルに応じたあなたの適切な年収を無料で診断しましょう。