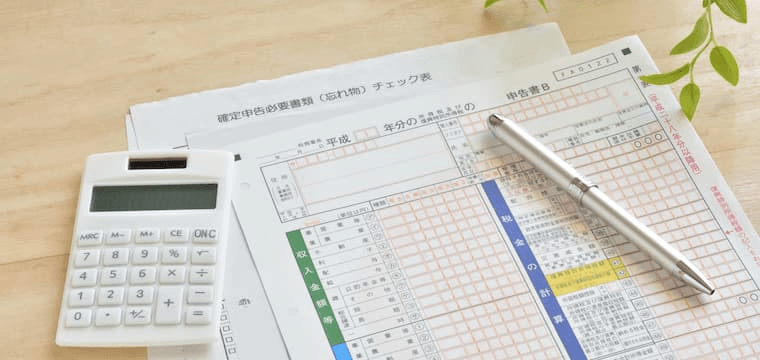目次
フリーランスなどの個人事業主になると、会社員のように年末調整はなく、毎年確定申告をして税金を納めることになります。確定申告には青色申告と白色申告があり、いざ自分がするとなると、違いが分からず、どちらで申告するのが良いか悩む人もいるのではないでしょうか。
この記事では、確定申告の青色申告と白色申告の違いや、それぞれのメリット・デメリットについて解説していきます。各制度に必要な書類や適している人についても紹介しますので、理解を深めて、自分にふさわしい申告方法を選んでください。
※時間がない方へ・・記事を読む時間が無い方でバックオフィス系の転職を検討中の方は、まずは「WARCエージェント」に無料登録してみましょう!
[:ad:]
確定申告とは?
確定申告とは、1年間の収入から経費などを差し引いて所得を算出し、所得に応じた所得税の金額を計算し、国(税務署)に申告する手続きのことです。所得税や法人税、消費税などを納めるために行うもので、個人事業主は所得税の確定申告が必要です。
確定申告では、毎年1月から12月までの1年間の売上や経費などを集計し、翌年の2月から3月に税務署に申告・納税します。個人事業主が行う確定申告には、大きく分けると青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告は事前に届出をして、所定の要件を満たした場合に税制上の優遇を受けることができる制度です。青色申告の承認を受けていない個人事業主が行う申告が、白色申告になります。白色申告は青色申告に比べ簡単に申告できますが、節税メリットはありません。
それぞれの違いの詳細については次章以降で解説していきます。
参考:国税庁「所得税の確定申告」
白色申告とは
白色申告とは「単式簿記」で行う確定申告方法です。単式簿記では、収支のみをつける、おこづかい帳程度の簡易な帳簿で申告できるため、青色申告に比べ簡単に申告できます。原則的な申告方法ですので、青色申告の申請・承認を得ていない場合は自動的に白色申告となります。
白色申告の場合は、申告の際に記載・提出する書類が少なく、準備する帳簿も最低限で良いとされています。そのため、日々の取引の記録なども手間がかからずに済むのがメリットです。
白色申告は、簡単に申告できる反面、特別な控除や特典がないため、同じ売上と経費であっても青色申告よりも税金額は高くなる可能性があります。
参考:国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」
青色申告とは
青色申告とは、事前に税務署に届け出ることによって選択できる申告方法です。青色申告では「複式簿記」もしくは「簡易簿記」で帳簿を記帳することが求められます。深い簿記の知識が必要となるため、慣れない人にとってはハードルの高い記帳方法といえるでしょう。
日々の取引の記録は、この複式簿記によって「仕訳帳」と「総勘定元帳」に記載していきます。正しく記帳した帳簿を揃え、決算書類の作成、必要な届出をするなど、いくつかの条件を満たすことで最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。
また、青色申告では赤字を繰り延べたり、家族の給与を経費にできるなど、他にも税制上の優遇を受けることが可能です。多くの特典があるため、節税に大変効果のある申告方法です。
参考:国税庁「No.2070 青色申告制度」
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告は以下のような違いがあります。
青色申告10万円控除 | 青色申告65万円控除 | 白色申告 | |
|---|---|---|---|
対象者 | 不動産所得、事業所得、山林所得があり、青色申告の承認を受けた人 | 青色申告の承認を受けていない人 | |
事前申請 | 開業届と青色申告承認申請書 | 必要なし | |
記帳方法 | 簡易簿記 | 複式簿記 | 簡易な方法 |
確定申告で必要な書類 | 確定申告書青色申告決算書(貸借対照表は作成義務なし) | 確定申告書青色申告決算書 | 確定申告書 |
必要な帳簿 | 現金出納帳売掛帳買掛帳固定資産台帳経費帳 | 【主要簿】総勘定帳仕訳帳【補助簿】現金出納帳売掛帳買掛帳固定資産台帳 など | 簡易な記載の帳簿 |
※青色申告の65万円控除は、e-Taxによる申告、または優良な電子帳簿保存を行っている場合に適用され、行っていない場合は、55万円控除になります。 | |||
この章ではそれぞれの項目について具体的に説明していきます。
対象者・事前申請の違い
青色申告するには、事前に税務署に申請し、承認を受けることが必要です。不動産所得、事業所得、山林所得があり、事前に申請し青色申告の承認を受けた人が青色申告を行えます。
会社員などで副業で収入がある場合などは、雑所得となり、対象外です。
青色申告の申請は、開業2ヶ月以内か、申告対象年度の3月15日までに行わねばならず、承認が間に合わなかった場合などは翌年からとなります。一度承認されれば、翌年からは申請は不要です。
青色申告の承認を受けていない人は、自動的に白色申告となります。白色申告は原則的な申告方法なので、申請は必要ありません。
帳簿の記帳方法の違い
青色申告と白色申告では必要な帳簿の記帳方法にも違いがあります。青色申告の場合は、2つの勘定科目を使った複式簿記形式で作成しなければなりません。日々の取引の記録は、「仕訳帳」と「総勘定元帳」に複式簿記の形式で正しく記帳することが求められます。
そのほか、「売掛帳」や「買掛帳」、「固定資産台帳」など補助的な帳簿の作成も必要になります。
一方、白色申告は、簡易簿記で、ひとつの勘定科目を使って現金の出入りを記録するだけでOKです。簿記の知識がなくても簡単につけられるため、おこづかい帳感覚で記帳できます。複式簿記のような複雑さがないため、領収書や請求書を見て、あとでまとめて記帳することも可能です。
必要な提出書類の違い
青色申告と白色申告では、確定申告で提出する書類も違います。青色申告では、確定申告書のほかに青色申告決算書を作成して提出しなければなりませんし、控除書類も必要です。
青色申告決算書は「貸借対照表」「損益計算書」などを記載する4枚から構成されています。これらを複式簿記で記帳した総勘定元帳などの内容を記載して作ります。
作成には専門的な知識が必要ですので、税理士に相談したり、会計ソフトを導入するケースも多いです。確定申告に対応した会計ソフトを使用すると、申告までが簡単に行えるようになっています。
白色申告の場合は、確定申告書と収支内訳書を提出すればよく、面倒な決算処理なども必要ありません。簡易な方法で記入した帳簿を元に、売上や必要経費を集計し、所定の収支内訳書に記載するだけで済みます。
税制上の優遇措置の違い
青色申告と白色申告では、税制上の優遇措置にも違いがあります。青色申告の場合は、10万円、55万円、65万円のうちいずれかの控除を受けることができます。これは「みなし控除」といわれ、領収書の要らない経費として売上から引くことができる制度です。
白色申告の場合にはこのような控除は受けられません。同じ収入であっても、控除が大きいほど納める税金は少額になりますので、青色申告の方が支払う税金額が少なくて済みます。
青色申告には他にも赤字を繰越すことができたり、10万円以上の固定資産を一括経費に計上できるなど、さまざまな税制上の優遇措置が受けられるようになっています。
青色申告のメリット・デメリットと適している人
ここでは青色申告のメリット・デメリットと、適している人について解説します。青色申告は、複式簿記での正しい記帳と申請の手間をかけることによって、大きなメリットが受けられることが特長です。
青色申告のメリット
青色申告にはさまざまな税制上の優遇措置や特典が用意されており、白色申告と比較すると多くのメリットがあります。
青色申告特別控除
青色申告には、青色申告特別控除という「みなし控除」があり、最大65万円の所得控除が受けられます。控除額には10万円、55万円、65万円の3種類があり、簿記の方法と提出する書類によって受けられる控除が異なります。
65万円の控除を受けるには、複式簿記で帳簿をつけ、貸借対照表と損益計算書の添付が必要です。これに加え、2020年度以降は電子申告もしくは電子帳簿保存が必要になりました。電子申告または電子帳簿保存ができない場合は、55万円の控除になります。
青色申告であっても単式簿記で記帳し、損益計算書をつけた簡易な申告の場合は10万円の控除となります。この場合は、貸借対照表の作成は義務付けられていません。
青色事業専従者給与
青色事業専従者給与とは、仕事を手伝ってくれた配偶者や家族に支払った給料を経費にできる制度です。白色申告にも「専従者控除」というものがありますが、これは最大でも配偶者が86万円、他の親族の場合は50万円までしか計上できません。
青色事業専従者給与なら、仕事に相応な金額であれば全額経費として認められますので、大きな金額を所得から控除できます。
利用する場合は、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していることが必要です。対象となる家族は、青色申告者と生計を一にしていることや、15歳以上であること、年間を通して半年以上の期間、青色申告者の営む事業に専ら従事していることなどの要件があります。
貸倒引当金繰入
青色申告では、売掛金や貸付金などの債権を合計した帳簿価額の5.5%以下を、貸倒引当金として経費に計上することができます。これは、後日代金を受け取る約束をした売掛金や貸付金が回収できないと思われる場合に、回収見込みがないとして処理する方法です。
このように債権の合計から計上する方法を「一括貸倒引当金」といいます。この他に「個別貸倒引当金」があり、白色申告の場合は個別貸倒引当金のみ繰り入れることが可能です。
本年度、貸倒引当金を計上し所得から控除した分は、代金が回収できた場合には次年度の所得に加える処理をします。
純損失の繰越しと繰戻し
青色申告では、1年の収支がマイナスになってしまった場合に、赤字(純損失)を3年間繰り越すことができます。
個人事業を始めてすぐは赤字になることが多く、翌年以降の黒字と相殺できればその分税金を安くすることが可能です。これにより2年目から4年目までの所得税を抑えることができるようになります。
さらに、純損失を繰り戻すことも可能です。前年度が黒字で今年が赤字になった場合に、赤字分を前年度の黒字から繰り戻して控除することができる制度で、これにより前年度の税金の還付を受けることができます。
少額減価償却資産の特例
通常、事業で購入した車やパソコンなどの固定資産は、10万円以上のものは減価償却を行うことになります。新車なら6年、パソコンなら4年などと個別に耐用年数が定められており、その期間で購入額を分けて計上する方法です。
減価償却を行うと、購入から経費として全額計上できるまでには長い時間がかかります。
事業を開始した当初は購入する物品なども多く、できるだけ経費に計上したい人も多いでしょう。
青色申告では30万円未満の固定資産は全額経費に計上できるため、高い節税効果があります。これを「少額減価償却資産の特例」といい、ひとつが30万円未満であれば、年間合計300万円まで計上できます。
青色申告のデメリット
メリットの大きい青色申告ですが、良い点ばかりではなく、申請や申告に手間がかかるというデメリットがあります。
事前に申請が必要
青色申告をするためには、事前に「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、承認を受けなければなりません。申請は開業から2ヶ月以内か、その年の1月1日から3月15日の間に、税務署に届け出ます。
承認までは時間がかかることがありますので、早めに申請するようにしましょう。一度申請すれば翌年以降も適用されますが、期限を過ぎると来年からの適用となる点には注意してください。
また、青色事業専従者給与を利用する場合も事前に申請が必要ですので、忘れずに届け出ておきましょう。新たに家族を雇った日から2ヶ月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に届け出ます。
白色申告よりも手間がかかる
青色申告は複式簿記で記帳しなければならないため、白色申告よりも記帳が複雑で、必要となる書類も多くなります。支出や収入を複数の科目で正しく記帳しなければなりませんし、年度末には損益計算書と貸借対照表の作成も必要です。
毎日の取引の記録を複式簿記の形式で記帳するため、簡易な簿記よりは時間や手間がかかります。正しく記載しなければならないため、専門的な知識が要求されます。間違いなく記帳し申告するために、税理士や会計ソフトを導入することも検討してみましょう。
青色申告に適している人
申請や記帳に手間がかかる青色申告ですが、どのような人が適していて、よりメリットを享受できるのか解説します。
白色申告で事業をしている人
白色申告で事業している人は、以前は利益が300万円以下であれば帳簿の作成や保存は不要でしたが、2014年より必要になりました。そのため、経理上の手間が青色申告の簡易簿記によるものと変わらない状況になっています。
白色申告から青色申告に変更することで、手間は変わらないのに10万円の控除が受けられ、他にも特典が利用できるようになります。これまで白色申告していた人も青色申告にすると多くのメリットがありますので、ぜひ一度検討してみてください。
事業(事業規模の副業含む)を始める人
青色申告はこれから事業を始める人にも適しています。事業を始めたばかりの頃は赤字が出やすいからです。青色申告にすると事業で出た損失を最大3年間繰越できますので、赤字が出やすい起業の初期こそ青色申告のメリットがあります。
開業届と一緒に青色申告の届出をすると、一度に手続きでき、あらためて税務署に届け出る必要もありません。
また、1年目の取引が少ない頃から複式簿記で記帳することで、取引や売上が増加した時にもあわてずに対応することができます。青色申告では多くの控除を利用できるので、黒字の場合も納める税金が少なくて済みます。
節税したい人
青色申告は個人事業主が利用できる非常に有効な節税方法です。青色申告特別控除のほか、純損失の繰越し・繰戻し、少額減価償却資産の特例など多くの特典があります。家族経営の事業の場合にも大きなメリットがあり、青色事業専従者給与制度によりすべて経費として計上可能です。
白色申告では一部しか控除されませんので、節税したい人はぜひ青色申告を行いましょう。
青色申告に必要な書類
青色申告する際に必要な書類は以下の通りです。どちらの書類も税務署の窓口でもらうか、国税庁のHPからダウンロードして使用しますが、スマホでも作成できます。
確定申告書
青色申告をする場合は、確定申告書第一表と第二表の記載が必要です。
第一表には年間の収入や所得、控除金額、税額などを記載します。青色申告の場合は、それぞれの金額は青色申告決算書から転記します。専従者給与額や青色申告特別控除の額なども決算書から転記しましょう。
氏名や生年月日、住所など基本的な情報のほか、マイナンバーや還付される税金の受取場所などの項目も記載が必要です。
第二表には、第一表の申告内容の内訳などを記載します。所得の内訳や、社会保険料の種類、配偶者や親族に関する事項、事業専従者に関する事項などを記入していきます。
青色申告決算書
青色申告決算書は、年間の収入や経費などをまとめた書類のことです。一般用様式と不動産所得様式、農業所得様式、現金主義様式の4種類があります。事業所得の場合は一般用様式を使用します。
青色申告決算書は4枚構成となっており、「貸借対照表」「損益計算書」のほか、減価償却の情報、売上等の内訳などを帳簿を元に記載しましょう。少額減価償却資産の特例を利用する場合は、「減価償却費の計算」を記入する際に、その商品の摘要欄に「措置法28条の2」と記入する必要があります。
貸借対照表は青色申告特別控除を受けるためには必須の書類ですので、正しく複式簿記形式で記入しましょう。尚、確定申告に対応した会計ソフトなら、自動計算や自動転記してくれ、手間がかからないようになっています。
白色申告のメリット・デメリットと適している人
次に、白色申告のメリット・デメリットと適している人を解説します。こちらは青色申告と比較してデメリットのほうが多めになっています。
白色申告のメリット
白色申告のメリットは以下の2つがあげられます。特別な特典などはなく、簡単で手間がかからないことが特長です。
申告が簡単
白色申告をする場合は、事前に申請する必要はありません。青色申告の申請をしていない人は自動で白色申告となるため、税務署に行って手続きしたり、申請のための準備をしなくて済みます。家族が仕事を手伝ってくれる場合に支払う給料に関しても、手続きなしで最大86万円まで経費に計上できます。
確定申告のために用意する帳簿や書類なども少なくて済みますし、記載の時間もかからず、簡単に申告できるのがメリットです。経理などが苦手な人でも取り組みやすい申告方法といえるでしょう。
簿記が簡単
白色申告では単式簿記による簡易な記帳で良いため、日々の取引記録も内容を簡単に記入するだけで済みます。おこづかい帳感覚で記帳できるため、納品書や請求書を見ながらまとめて記帳することも可能です。確定申告の際は、勘定科目ごとの合計を収支内訳書に記入するだけでOKです。
青色申告で求められる複式簿記のような複雑さがないため、簿記の知識がなくても容易に申告できるでしょう。しかし、近年では会計ソフトを用いることで、簿記の知識が少なくても帳簿をつけることが可能になってきました。以前と比べ複式簿記で記帳するハードルは下がっているといえるでしょう。
白色申告のデメリット
ここでは白色申告のデメリットをみていきましょう。主なデメリットは、控除や適用される特典が少ないことがあげられます。
控除が受けられない
白色申告では青色申告特別控除のような「みなし控除」はありません。そのため、同じ収入であっても納める税金額が大きくなるというデメリットがあります。税金が高くなるだけでなく、健康保険料なども変わってきますので、トータル考えると大きな違いが出てくるといえるでしょう。
また、仕事を手伝った家族に支払う給料についても青色申告より控除額は少なくなります。
白色申告の事業専従者控除は、事業主の配偶者であれば86万円、それ以外の親族などは1人につき50万円が上限ですので、青色申告のように支払った分すべてを経費として計上できるわけではありません。
赤字の繰越しと繰戻しができない(一部繰越可能)
白色申告では青色申告に可能な赤字の繰越しなどもできません。個人事業を始めたばかりの頃は赤字になるケースが多く、特に大きな赤字が出るような事業の場合は、繰越せないことは大きなデメリットといえるでしょう。
一般の事業であっても、赤字を繰越したり繰戻しできる青色申告の方が、数年に渡る節税効果が期待できます。ただし、白色申告であっても災害の影響などが考えられる場合には、繰越し制度が利用できるケースもあります。
貸倒引当金を計上できない(一部計上可能)
白色申告では青色申告のように債権の合計額から算出した一括貸倒引当金の計上はできません。これは青色申告者の特典とされているからです。貸し倒れは個人事業主にとって大きなリスクであり、それに備える制度はできれば利用したいものです。
ただし、白色申告の場合でも個別に貸倒引当金を計上することは認められています。後日、債権を回収する予定があるが、回収不能と予測される場合には、個別貸倒引当金を繰入できます。
少額減価償却資産の特例を使えない
白色申告では少額減価償却資産の特例も使えません。10万円以上の固定資産を購入した場合は、「定額法」または「一括償却資産」として数年かけて経費に計上していきます。
これによって、青色申告と比較して、同じ固定資産を購入してもその年に引くことのできる経費が少なくなり、税金額が増える可能性があります。事業の開始当初など固定資産の購入が多く、当年分の経費としてできるだけ計上したい場合は、青色申告がオススメです。
白色申告に適している人
白色申告に適している人は、経理作業が苦手で、確定申告などもできるだけ簡略化したい人です。青色申告では日々の取引を複式簿記で記帳しなくてはならず、苦手な人や知識がない人にとっては難しく、時間もかかってしまうからです。
記帳の手間を省くために、会計ソフトを導入することもひとつの方法です。しかし、その場合であっても、事前の承認申請の手間もなく、帳簿もまとめて簡単につけられるため、簡便さに魅力を感じる人は白色申告の方が向いています。
白色申告で確定申告する際に必要な書類
白色申告で確定申告する際に必要な書類と記載内容について解説します。こちらも税務署の窓口でもらうか、国税庁のHPからダウンロードして使用しますが、スマホでも作成できます。
所得税の確定申告書
白色申告の場合も確定申告書第一表と第二表の記載が必要です。
第一表には年間の収入や所得金額、基礎控除や社会保険料控除の金額、税額などを記載します。白色申告の場合は、一緒に提出する収支内訳書から転記します。専従者給与額なども収支内訳書から転記しましょう。記載した所得を元に税額を算出します。
その他、氏名や生年月日、住所など基本的な情報のほか、マイナンバーや還付される税金の受取場所などの項目も記載が必要です。
第二表は、第一表の申告内容の内訳などを記載する場所です。所得の内訳や、社会保険料の種類、配偶者や親族に関する事項、事業専従者に関する事項などを記入していきます。
白色申告の場合は控除額が少ないため、生命保険料控除やふるさと納税(寄付金控除)など当てはまるものはもれなく記載しましょう。
収支内訳書
白色申告の場合は、決算書ではなく収支内訳書を提出します。収支内訳書には一般用様式と不動産所得様式、農業所得様式の3種類があり、事業所得の場合は一般用を使用します。収支内訳書は2ページあり、主に以下の内容の記載が必要です。
- 収入
- 売上原価
- 経費の内訳
- 減価償却の計算
- 事業専従者の氏名や給料賃金の内訳
2ページ目は1ページ目の内訳になります。それぞれの項目を、売掛帳や買掛帳、経費帳、固定資産台帳などを見ながら記載していきます。確定申告の際には毎年記載する項目ですので、これらのわかる書類や帳簿をきちんと準備し、保存するようにしましょう。作成した帳簿の保存期間は7年が義務化されています。
手間はかかるがメリットの多い青色申告を検討してみよう
青色申告は、取引内容を複式簿記で行わねばならず、申請が必要なものも多いため、白色申告と比べ手続きが煩雑になります。しかし、その分さまざまな特典が受けられ、大きなメリット・節税効果が期待できる申告方法といえるでしょう。
近年普及している会計ソフトや税理士を利用すると費用はかかりますが、正しい方法で青色申告することができます。費用と効果を考慮して、青色申告と白色申告のどちらを利用するか検討しましょう。
青色申告の申請をしていても白色申告することは可能ですので、とりあえず青色申告の申請をしておくのもひとつの方法です。
ビジネスに関する記事一覧
働き方の関連記事
給与・確定申告などの関連記事
ビジネスの関連記事
[PR]"好条件"の管理部門転職なら
管理部門・バックオフィスで転職するならSYNCA(シンカ)。
経理、総務、法務、労務、情シスなどの職種や細やかなスキル設定により 採用企業から一人ひとりに合ったスカウト求人が直接届きます。
まずはスキルに応じたあなたの適切な年収を無料で診断しましょう。