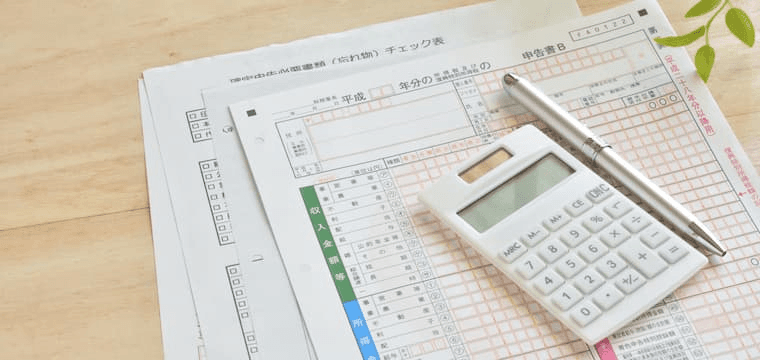目次
医療費控除は、確定申告で設定されている控除の1つです。納税者本人だけでなく、納税者の家族にかかった医療費にも適用されます。医療機関に支払った費用のほか、医療機関までの交通費、薬局で販売しているスイッチOTC医薬品の購入費など、医療に関するさまざまな費用が対象になるのがポイントです。
この記事では、医療費控除の対象・申請期間・対象となる医療費・申請方法を解説します。還付金の計算方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
※時間がない方へ・・記事を読む時間が無い方でバックオフィス系の転職を検討中の方は、まずは「WARCエージェント」に無料登録してみましょう!
確定申告の「医療費控除」とは
確定申告の医療費控除は、所得控除制度の1つです。控除を受けられる医療費の上限は200万円で、申請前年の1年間にかかった医療費が10万円以上の方・総所得金額が200万円未満で医療費が占める割合が5%以上になると控除対象になります。控除の対象者・対象となる経費などは以下に解説するとおりです。
参考:【初心者向け】確定申告のやり方は?流れや必要書類を解説
医療費控除の対象者
医療費控除の対象者は、納税者本人と納税者と「生計を一にする」(※1)家族全員と定められています。生計を共にしている方であれば、家族以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族・里子・養護老人)も対象です。控除の対象に入れられる家族を具体的に紹介します。
(※1)参考:国税庁「扶養家族」
- 下宿をしている大学生
- 同居している社会人の子ども
- 別居していて納税者本人が仕送りをしている親
- 遠隔地の病院等で治療・療養している家族
「生計を一にする」とは日常生活の費用を共にしている意味で、納税者本人が扶養している方なら同居の有無は問われません。逆に、家族であってお互いに経済的に独立した生活をしていると、医療控除の対象者と認められなくなります。
共働きでお互いに所得がある場合
扶養家族にしていない共働きの夫婦でも、生計を一にしていれば医療費控除の対象です。1年にかかった医療費の総額を、夫婦どちらかの申請書に付けて申告しましょう。共働きで医療費控除額でなるべく多く還付金を得るには、医療費の合計額が10万円以上・10万円未満で申請者を変えるのがオススメです。
1年間にかかった医療費 | オススメの申請者 |
医療費を合計して補填された分を引いて10万円を超える | 夫婦で所得が高い方 |
医療費を合計して補填された分を引いて10万円に満たない | 夫婦で所得が200万円未満の方 |
一般的に、医療費控除は所得が高い方が申請すると税率が高くなり、還付金も高くなります。しかし、夫婦のどちらかの課税所得が200万未満の場合は、医療費控除を受ける条件の「医療費が占める割合が5%以上」に該当する可能性が高くなるので、所得が低い方が申請しましょう。
医療費控除の対象となる費用
医療費控除の対象として認められる費用は、非常に多いのがポイントです。中でも、ぜひ知っておきたい控除対象を10点、以下に紹介します。
- 医療機関(医師・歯科医師)で支払った診療費・治療費(保険外治療・インプラントも含む)
- 入院費用(部屋代や食事代など)
- 妊婦の定期健診・出産後の検診費用
- 不妊治療・人工授精の費用
- 医師の処方箋で購入した医薬品の費用
- 治療に必要な松葉杖などの購入費用
- 通院に必要な交通費
- あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師・鍼師・灸師によるリハビリやマッサージの費用
- 介護保険の対象となる介護費用
- スイッチOTC医薬品の購入(世帯合計で12,000円以上)
交通費は、市バスなど公共交通機関ならすべて認められるので、レシートをまとめておきましょう。タクシー・新幹線・飛行機は、患者の病状や居住地から医療機関からの距離などを考慮して、必要と判断されれば適用されます。付き添いの方にかかった交通費が認められるのは、患者が1人で移動するのが困難な場合のみです。
医療費控除の対象とならない費用
医療費控除には、控除の対象にならない費用もあります。具体的なものを以下に紹介するので、参考にしてください。
- 美容整形の費用
- 医療目的ではない歯科矯正の費用
- 健康診断・人間ドックの受診費
- 医師の処方箋によらない眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器の購入費
- 治療目的ではない予防接種・サプリメント・漢方薬の費用
- 里帰り出産のための交通費
- 自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代・有料道路の通行料
- 入院時、自己都合で個室を選んだ場合の差額ベッド代・散髪代・テレビのレンタル代等
- 入院に付き添った家族・親族の食事代
- 介護などをしている家族・親族に御礼として支払ったお金
医療費控除が適用されない費用は、病気の治療と直接関係のない物事にかかった費用と覚えておきましょう。しかし、健康診断や人間ドックの費用は、受診した結果、治療が必要な病気が見つかれば医療控除の対象として認められます。
医療費補填金
医療費補填金とは保険金等、病気やけがをしたときに生命保険や健康保険等から支給されるお金です。給付を受けた場合は確定申告で給付額を申請する必要があるので、証拠となる書類等を必ず残しておきましょう。医療費補填金には、以下のようなものがあります。
保険の種類 | 支給される医療費補填金の種類 |
生命保険 | 入院給付金・手術給付金・傷害費用保険金・通院給付金・女性疾病入院給付金等 |
健康保険 | 高額療養費・傷病手当費・療養費・出産育児一時金・入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・移送費等 |
医療費補填金は対象の疾病の治療にかかった医療費に対して支払われるものです。控除額を計算する際は、1年の医療費総額からではなく、対象の疾病にかかった費用から医療補填費を引いてください。また、医療費補填の金額は、実際の医療費より上回った場合でも申請書に記載が必要です。
確定申告の「医療費控除」申告期間と期限は
医療費控除の申告は確定申告と一緒に行います。年末調整をしている会社員等、確定申告の義務がない方は還付申告をして払いすぎた税金を還付してもらいましょう。また、医療費控除は5年分までさかのぼって申告できます。
申告期間
個人事業主等で年末調整がない場合、医療費控除は前年の所得などと一緒に確定申告の申請書に記載して申告します。申告期間は、原則、確定申告期間(毎年2月16日~3月15日)と同じです。申告期間が始まるまでに書類をそろえ、金額を計算して申請書に記入しておきましょう。
万一、確定申告の申請期間に間に合わなかった場合は、申告する予定だった年から5年以内に申告してください。医療費控除は5年間さかのぼって申告できます。たとえば、2023年に支払った医療費については、2028年の1月1日~12月31日まで申告可能です。
また、医療費控除の申告は万一遅れても、ペナルティは課されません。
還付申告の期限
医療費が多かった場合、医療費控除の還付申告をすると税金の還付が受けられます。年末調整を受けている会社員等の方はご自身で、源泉徴収票・医療費の明細書・確定申告申告書を税務署に提出しましょう。
医療費控除の還付申告は、確定申告の申請期間中でも受け付けてもらえます。しかし、還付申告の期限は所得税などと違い、申告する予定だった年から5年以内です。還付申告は毎年12月31日まで受け付けてもらえます。混雑を避けたい方は、e-Tax・郵送のほか確定申告期間の時期を避けて所轄の税務署まで書類を提出しに行くのがオススメです。
控除額と還付金の計算方法は
医療費控除の所得控除額と還付金の計算方法は、「所得金額合計が200万円」以上か未満かで異なります。それぞれ計算式も一緒に紹介するので、参考にしてください。
所得金額合計が200万円以上の場合
前年の所得金額合計が200万円以上だった場合、支払った医療費が所得金の5%か、10万円までが医療費控除額として認められます。所得金額合計が200万円で支払った医療費合計が30万円の場合、医療費控除として申告できるのは、30万円ー10万円=20万円です。
また、実際に所得控除を計算する際は、医療費控除額10万円だけでなく、生命保険会社等から支給された医療費補填金の金額も引く必要があります。所得金額合計が200万円以上だった場合は、以下の数式を使って控除に申告できる金額を計算しましょう。
- 医療費控除の金額=(1年に支払った医療費 - 医療費補填金額)- 10万円
所得金額合計が200万円未満の場合
前年の所得金額合計が200万円未満だった場合は、所得金の5%までを医療費控除の金額として認められます。たとえば、所得金額が180万円なら180万円×5%=9万円で、医療費の還付申告ができる金額は9万円です。
所得が200万円未満であっても、医療費補填金の給付があった場合は医療費から医療費補填金の金額を引いて控除額を算出してください。所得金額合計が200万円未満だった場合は、以下の式を使って控除を申告できる金額を計算します。
- 医療費控除の金額=(その年に支払った医療費 - 医療費補填金額)- 所得金額の5%
実際に戻ってくる金額の計算方法
所得合計から医療費控除の還付金額を計算するには、以下に紹介する手順で計算しましょう。
- 前年の所得合計が200万円以上か、200万円以下かを確認する
- 医療費控除額を計算する
- 所得合計200万円以上:支払った医療費の合計ー医療費補填金額金額ー(10万円または総所得の5%でどちらか少ない方)
所得合計200万円以下:支払った医療費の合計ー医療費補填金額ー総所得の5%
- 課税所得税を計算する(給与所得を得ているのが1か所のみの場合)
給与所得控除後の金額ー所得控除の合計=課税所得税
- 還付金を計算する
- 医療費控除額ー所得控除の合計=還付金(実際に返ってくる金額)
還付金額は、医療費控除対象額(上限200万円)×所得税率(5%~45%)で計算する方法もあります。
確定申告「 医療費控除」の申告の流れ
医療費控除を申請するには、書類の準備から還付金の返還まで一連の流れを理解しておくとスムーズです。以下に紹介するので参考にしてください。
ステップ1:まず医療費控除を受けられるか確認
医療費控除を申請すると決めたら、始めに、自分に所得税の納税義務があるかを確認しましょう。医療費控除の還付を受けるには、所得税の納税者である・1年間に一定以上の医療費を支払っている、の2点を満たしている必要があります。
個人事業主やフリーランスなら、前年の所得が49万円以上ある方です。給与所得者の場合は、源泉徴収票で自分が所得税を納税しているかをチェックしてください。
医療費控除を受けられる医療費は、年間所得が200万年以上なら「医療費控除の金額=(1年に支払った医療費 - 医療費補填金額)- 10万円」、年間所得が200万円以下なら「医療費控除の金額=(その年に支払った医療費 - 医療費補填金額)- 所得金額の5%」で計算できます。
ステップ2:医療費控除額と還付額を計算
医療費控除を受けられる金額が計算できたら、続いて実際に受け取れる還付額を計算しましょう。還付額は「医療費控除金額×所得税率」で計算できます。
所得税率は5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%と7段階で設定されていて、所得額が高いほど税率が高くなるのが特徴です。所得税率は時々改定されるので、毎回国税庁のサイト(※1)でチェックしましょう。
(※1):参考 国税庁「所得税の税率」
医療費控除額の計算方法は、前項を参考にしてください。
ステップ3:確定申告書と医療費控除の明細書作成
医療費控除額の計算ができたら、確定申告書と医療費控除の明細書を作成しましょう。それぞれの用紙は税務署の窓口か国税庁のサイト(※2)で手に入ります。自宅のPCやスマホから申請するなら、国税庁のサイト「確定申告等作成コーナー」(※3)から直接申請しましょう。
(※2):参考 国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
(※3):参考 国税庁 「確定申告書等作成コーナー」
医療費控除の書類は先に医療費控除の明細書を書き、後で確定申告書を書くのがオススメです。医療費控除の明細書は、医療費通知に関する事項・医療費の明細・控除額の計算と書くべき内容が多く計算も複雑になっています。計算が苦手な方や早く作業を終わらせたい方は国税庁の医療費集計フォーム(※4)を利用しましょう。
(※4):参考 国税庁「医療費集計フォームのダウンロード」
医療費控除の記入欄は確定申告書の第一表にあります。「医療費の明細」で記入した医療控除費控除額と同じ金額を所定の欄に記入してください。
ステップ4:所轄の税務署に提出
確定申告申請書・医療費控除の明細書が完成したら、所轄の税務署に提出しましょう。提出方法は税務署や確定申告の会場に行く・e-Tax・郵送の3つあります。個人事業主やフリーランスの方は必ず、2月16日~3月15日の間に設定される確定申告期間に申請してください。給与所得者で医療費控除の申請をする場合は、1年の間で時間のある時に申請しましょう。
医療費控除の申請には、以下の書類が必要ですので忘れずに確定申告の会場まで持参してください。以前は医療費の領収書も提出が必要でしたが、近年は提出不要になりました。しかし、医療費の領収書は医療費控除申請後5年間、自宅で保管が必要です。
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
- 源泉徴収票
- マイナンバーなどの本人確認書類
ステップ5:還付金を受け取る
医療費控除の申告が終わったら、還付金が帰ってくるのを待ちましょう。還付金は医療費控除の申告から1か月~1か月半後に指定した銀行口座・ゆうちょ銀行口座に振り込んでもらうか、郵便局の窓口で手渡ししてもらうかいずれかの方法で受け取ってください。
還付金の振り込みをされたり、受け取り可能になる前後になると、税務署から通知書が郵送されてきます。通知書には還付金の金額が記載されているので、通帳の記録などと照らし合わせて振り込まれた金額に間違いがないか確認するのに利用してください。
医療費を多く支払ったら必ず医療費控除を申請しよう
医療費控除の申請方法は非常に簡単です。所得税の納税者であれば、個人事業主やフリーランスだけでなく給与所得者も申請できるので、前年の医療費が多かった方はぜひ申請しましょう。
医療費控除は生計を一にしている家族・親族の分をまとめて申請可能なうえ、対象と認められる経費は非常に幅広いのもポイントです。また、医療費控除は、所得に応じて申請する方を変えると、より多くの還付金を受けられるようになります。
ビジネスに関する記事一覧
働き方の関連記事
給与・確定申告などの関連記事
ビジネスの関連記事
[PR]"好条件"の管理部門転職なら
管理部門・バックオフィスで転職するならSYNCA(シンカ)。
経理、総務、法務、労務、情シスなどの職種や細やかなスキル設定により 採用企業から一人ひとりに合ったスカウト求人が直接届きます。
まずはスキルに応じたあなたの適切な年収を無料で診断しましょう。