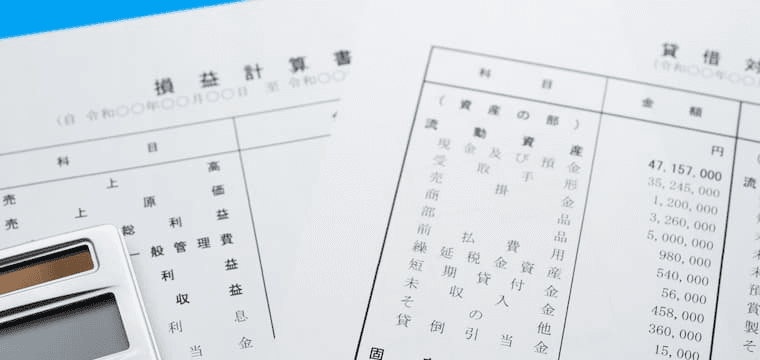目次
損益計算書は、会社の一定期間の損益を知ることができる決算書類のことです。
この記事では、損益計算書の概要や見方、チェックすべき項目について詳しく解説しています。損益計算書が読めるようになると、会社がどれくらい儲けて、損失が生じたかがわかり、会社の収益性についての分析に役立てることができます。
損益計算書の活用方法が知りたい経営者や経理担当者の方は参考にしてみてください。
※時間がない方へ・・記事を読む時間が無い方でバックオフィス系の転職を検討中の方は、まずは「WARCエージェント」に無料登録してみましょう!
損益計算書とは
損益計算書とは、「期間ごとの経営成績(儲け具合)を表すもの」です。つまり、一定期間にどれだけの収益をあげて、どれだけ費用がかかったのか。その結果として、どれだけの儲け(利益)を獲得したのかが集計されます。損益計算書は、収益・費用・利益の3つの要素で構成され、英語では「Profit & Loss Statement」といい、この頭文字をとって「P/L」と呼ばれます。
収益 - 費用 = 利益 |
損益計算書では、左側(借方)に費用をまとめ、右側(貸方)に収益をまとめます。費用の合計額と、収益の合計額には差が生じますが、この差は利益または損益にあたります。この利益または損失と、収益及び費用を合計することで借方と貸方が一致します。
損益計算書を読むことで、利益を上げているものが本業と本業以外なのか、会社が利益をあげるためにどのように努力をしているかがわかります。
損益計算書と貸借対照表の違い
損益計算書は、「ある一定期間」の経営成績を示し、貸借対照表は「ある一定時点」における企業の資産、負債、純資産の状況を把握できます。
資産 = 負債 + 純資産 |
貸借対照表は、ある特定時点での企業の資産と負債を示す財務報告書です。これは、企業の財務状態を示し、資産(現金、債権など)と負債(借入金、未払費用など)の残高を表示します。
損益計算書と貸借対照表の違いですが、損益計算書は動的なデータであり、特定期間内の業績を示します。一方、貸借対照表は静的なデータで、特定時点の企業の財政状況を示しています。
これら2つの報告書は、企業の健全性を評価するための重要な書類であり、一緒に読み解くと会社の経営状況を深く理解することができます。
損益計算書の見方
損益計算書は、会社の経済的な活動と業績を評価するための財務報告書の重要な部分です。
この書類では、会社がある特定の期間内でどれだけの収益をあげ、それに対してどれくらい費用が発生したかを示します。
ここでは損益計算書の基本的な構成要素と、それを解釈する方法について解説します。企業の収益力や収益源、費用の構成、利益の安定性を理解するために、損益計算書の見方を学びましょう。
経常損益の部
経常損益の部は、企業の業績評価において重要な要素であり、「営業損益」「営業外損益」「経常利益」の3つにわけられます。
これらの要素を理解することは、企業の経営戦略や業績向上のために不可欠です。以下で、経常損益の部の3つの要素について解説します。
営業損益
営業損益とは、企業の本業である営業活動によって得られた損益のことです。ここで「売上総利益」と「営業利益」を算出することができます。
<売上総利益>
売上総利益は、売上高に商品の原価である売上原価を差し引いたものです。一般的に粗利益(粗利)と言われているように、本業の大元の利益のことをいいます。
売上総利益 = 売上高 - 売上原価 |
売上は、商品の販売やサービスの提供など、会社の本業の営業活動によって得られる収益を指し、「売上高」とも呼ばれます。売上原価は、商品の仕入や、製造する際にかかる費用のことで、売上原価が小さければその分儲けは大きくなります。
製品・商品の収益力を表し、通常の商売で売上総利益がマイナスになることはまずあり得ません。なぜなら、マイナスになるとすれば、「売上<原価」となり、原価割れしていることになってしまうからです。
<営業利益>
次に、営業利益とは、売上総利益から販売費および一般管理費を差し引いたものになります。販売費および一般管理費は、商品やサービスを販売・管理する上でかかる経費のことです。たとえば、従業員の給料や広告宣伝費、運送費、店舗の賃料などがそれにあたります。
営業利益 = 売上総利益 - 販売費および一般管理費 |
営業利益は、本業での営業活動の成果として得られた利益のことであり、利益となった場合には営業利益、損失となった場合には営業損失となり、損益計算書に記載されます。
営業外損益
営業外損益とは、通常の営業活動に直接関連しない収益や費用を示す項目です。この部分は、会社が日常業務以外の出来事や活動から生じた収益や費用を納めています。
営業外損益 = 営業外収益 - 営業外費用 |
営業外損益の主な要素として、「営業外収益」と「営業外費用」があります。
<営業外収益>
営業外収益とは、本業の営業活動から発生しない収益のことです。たとえば、受取利息や配当金、株取引の利益などです。
<営業外費用>
営業外費用とは、本業の営業活動には関連しない費用のことを指します。たとえば、支払利息や為替差損といったものが含まれます。
営業外損益は、会社の総合的な業績を評価する際に重要であり、通常の営業活動以外での要因が会社の収益性や損益にどのように影響を及ぼしているかについて示しています。
経常利益
経常利益とは、営業利益に営業外収益を加え、営業外費用を差し引いて求められます。
経常利益 = 営業利益 + (営業外収益 - 営業外費用) |
<営業外収益>
営業外収益とは、本業以外で獲得した収益のことです。たとえば、預金の利息や家賃収入、配当金などです。
<営業外費用>
営業外費用とは、費用を示します。たとえば、借入金の支払利息などです。
経常利益と営業利益の差から、本業以外でどれだけ儲けがあるのかが把握することができ、継続的に行われる活動により獲得した利益のため、会社の実力が1番反映される利益と言われています。
特別損益の部
特別損益の部とは、臨時・突発的に発生する利益や損失のことです。これらは通常の営業活動とは異なる事象に関連して発生し、企業の実際の業績に影響を与えます。特別損益には、「特別利益」と「特別損失」にわけられます。
<特別利益>
会社の本業とは関係なく臨時的に発生した利益のことです。たとえば、不動産売却による「固定資産売却益」など、通常は発生しない利益になります。
<特別損失>
会社の本業とは関係なく臨時的に発生した損失のことです。たとえば、保有している株式の「売却損」や、火災・自然災害などによる「災害損失」などです。
特別損益の目的は、通常の営業活動から生じる利益や損失とは別に、特別な事象による収益や費用をはっきりと表示することです。これにより、通常の営業活動と特別な要因による業績を区別し、企業の持続可能性や将来予測を分析することができます。
その他の部100
その他の部は、「税引き前当期純利益」「当期純利益」の2つにわけられます。この2つは会社の財務諸表で表示される利益に関連する項目です。以下で、その他の部の2つの要素について解説します。
税引前当期純利益250
税引前当期純利益とは、経常利益に特別利益を加え、特別損失を差し引いたものをいいます。
税引前当期純利益 = 経常利益 - (特別収益 - 特別損失) |
税引前当期純利益は、本業の営業活動での利益のほか、営業外損益や一時的な損益である特別損益までを含み、法人税や住民税、事業税といった税金コストは含みません。金額がマイナスの場合には、税引前当期純損失といいます。
当期純利益
当期純利益とは、税引前当期純利益から、法人税、法人住民税、法人事業税を差し引いたものをいいます。
当期純利益 = 税引前当期利益 - 法人税等(法人税+法人住民税+法人事業税) |
当期純利益は、会社がその期間中に全ての収益と費用、利息費用、税金等を考慮に入れた最終的な利益を表します。この数字がマイナスであれば赤字、プラスであれば黒字になります。
当期純利益は、会社が1年間の経営活動の中での最終的な利益を示すものですが、一概に当期純利益が多く、黒字であれば問題ないとは言い切れません。なぜなら、当期純利益には、臨時的な収益や損失が含まれ、また税額は前会計年度の所得によるものだからです。
当期純利益は、企業の重要な指標ではありますが、その内訳がどのようなものになっているかを見ることが重要です。
損益計算書でチェックすべきポイント
これまで損益計算書の見方について解説しましたが、実際に損益計算書のどこに注目してみればいいかわからない方もいらっしゃいますよね。そこで、次に損益計算書で特にチェックすべきポイントについて3つ解説します。
売上総利益率
売上総利益率とは、売上高から費用や原材料費などの変動費用を差し引いた後の売上総利益を売上高で割ったものです。
売上総利益率(%) = 売上総利益 ÷ 売上高 × 100 |
総利益率が高いほど、企業は売上からコストを効率的に管理しており、収益性が高いことを示しています。逆に、低い総利益率は、高いコストや低い価格設定に起因し、利益が限られていることを示しています。
売上総利益率の平均値は業界ごとによって異なりますが、推移を確認したり同業他社と比較したりすることで、自社の販売戦略や価格設定が正しいかどうかを判断できます。
売上高営業利益率
売上高営業利益率は、企業が本業で稼いだ営業利益を売上高で割った割合を示します。
売上高営業利益率(%) = 営業利益 ÷ 売上高 × 100 |
この率は、企業が営業活動を通じてどれだけ利益を上げているかを示します。高い営業利益率は、企業が売上高に対して効率的に経費を管理し、収益性が高いことを示しています。逆に、低い利益率は、高い営業費用や低い価格設定によるもので、利益が限られていることを表しています。
営業利益率は、業種にも異なりますが10%を超えていれば優良といわれています。企業はこの利益率を重視し、収益性を向上させるために経費削減、価格戦略の見直し、収益向上策などを検討します。
売上高経常利益率
売上高経常利益比率は、売上高から営業外費用を差し引いた経常利益を売上高で割ったものです。
売上高経常利益率(%) = 経常利益 ÷ 売上高 × 100 |
経常利益は、営業活動とそのほかの要因を考慮した収益であり、企業の本業による活動だけでなく、外部要因も含めた利益を示します。
売上高経常利益率が高いほど、企業は営業活動において収益を高めており、適切なコスト管理を行っていることを表しています。利益率が0%を下回る場合は赤字状態であり、収益を上げたり費用を抑えたりする必要があります。この比率は、企業の経営効率と収益性を評価する指標であり、経常的な利益を売上高に対して評価しています。
損益計算書を分析して、会社の成長に貢献しよう
損益計算書は、企業や組織の特定期間内での収益と費用を記録する財務諸表です。損益計算書を理解して活用するためには、以下のポイントに注目します。
- 収益(売上高):企業の主要な成功指標のひとつ
- 費用:人件費や原材料費、運転費用、支払利息など
- 総利益:収益から総費用を差し引いたもので、企業の実際の利益を示す
- 純利益:所得税などの税金が差し引かれた後の利益
- 利益率:総利益を売上高で割ったもの
これらの数字が正しいかを確認し、前年度との比較を行います。
損益計算書が分析できるようになると、会社がどれくらいお金を使ったのか、どのような理由で儲けることができたのか、赤字があるかどうかなどの経営状態を把握することができます。
損益計算書は、経営戦略や財務の健全性、投資判断などに重要な書類です。損益計算書を正確に分析し、経営判断に役立ててください。
ビジネスに関する記事一覧
働き方の関連記事
給与・確定申告などの関連記事
ビジネスの関連記事
[PR]"好条件"の管理部門転職なら
管理部門・バックオフィスで転職するならSYNCA(シンカ)。
経理、総務、法務、労務、情シスなどの職種や細やかなスキル設定により 採用企業から一人ひとりに合ったスカウト求人が直接届きます。
まずはスキルに応じたあなたの適切な年収を無料で診断しましょう。