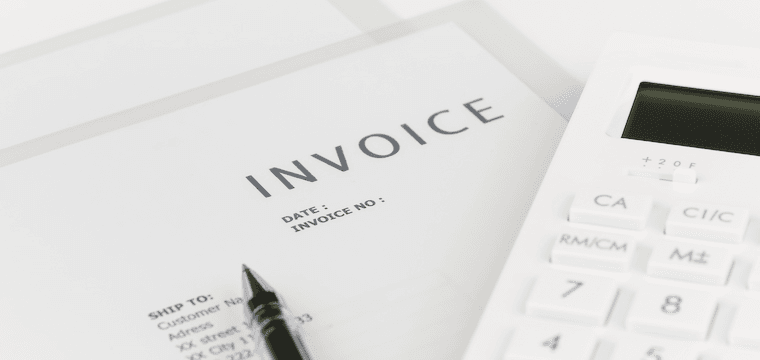目次
2023年10月1日より、インボイス制度がスタートしました。しかし、「ニュースなどでよく耳にするけれど、詳しい内容はわからない」「自分にも何か影響があるのだろうか」と疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。
この記事ではインボイスとは何なのか、またインボイス制度の概要や、制度への対応方法などについて解説しています。ぜひ最後まで目を通して、インボイス制度への理解を深めてください。
※時間がない方へ・・記事を読む時間が無い方でバックオフィス系の転職を検討中の方は、まずは「WARCエージェント」に無料登録してみましょう!
インボイスとは?
インボイス(※1)は適格請求書とも言い、事業者間の取引において売り手側が買い手側に対し、正確な消費税の適用税率や税額を伝える手段です。従来の請求書と比較すると消費税に関する詳しい記載が必要であり、消費税の計算方法も変わっています。
インボイスは請求書だけでなく、納品書・領収書・レシートなど名称を問わず、一定の事項が記載された書類はすべてインボイス扱いとなります。事業者間の取引に関する書類ですので、一般の消費者には特別な影響はありません。
(※1)参考:国税庁「インボイス制度の概要」
従来の請求書との違い
従来の請求書のことを「区分記載請求書」といい、インボイスはこれに必要な項目を追加した形式になります。「区分記載請求書」の記載事項は以下の6つの項目です。
- 発行者の氏名、又は名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 受領者の氏名、又は名称
- 軽減税率の対象である旨の表記(対象商品に※マークをつけるなど)
- 適用税率ごとに区分した商品の合計額
インボイスで追加される項目は以下の3つになります。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 適用税率
- 適用税率ごとの消費税額の合計
不特定多数に対して販売やサービスを行う飲食店や小売業などは、記載事項を簡略化した「簡易インボイス(適格簡易請求書)」を交付できます。
インボイスが必要な理由
インボイスによって取引の際の正確な消費税率と税額の把握ができます。これまでは仕入れる商品には通常の税率のものと軽減税率が適用されたものが混在している状態でした。
複数の税率に対する納税額を正しく計算するためには、各取引の商品ごとに適用税率を明確にする必要があります。インボイスの発行により、商品ごとの正しい消費税額が計算・把握できるようになり、ミスや不正を防ぐことがインボイス制度の目的です。
インボイスを交付可能な事業者
インボイスを発行するには適格請求書発行事業者登録が必要です。適格請求書発行事業者登録は、消費税の納税義務がある課税事業者だけが行なえます。
本来、売上が1,000万円未満の場合は免税事業者となるのですが、免税事業者であっても取引先からインボイスを求められれば発行しなくてはなりません。その際には免税事業者はまず課税事業者になるための手続きをしてから登録申請に進みます。
免税事業者から課税事業者になると納税義務が発生するほか、経理事務が煩雑になるデメリットがあります。適格請求書発行事業者登録をするかどうかは取引先とも相談し、慎重に検討しましょう。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」といい、消費税の仕入税額控除の方式の一つです。現在、消費税は原則税率10%ですが、食品など一部の商品には軽減税率が適用され8%になっており、これまでの請求書は適用税率が混在していました。
適用する税率や税額の記載を義務付けた請求書が「インボイス」であり、仕入れ先などが発行するインボイスを保存しておくことではじめて消費税の仕入税額控除が受けられるようになる制度がインボイス制度です。
インボイスがないと仕入税額控除が受けられなくなるため、要求された場合はインボイスを発行しなくてはなりません。
仕入税額控除について
消費税は、原則として課税される期間中の売上の際に預かった消費税(売上税額)から、仕入れの際に支払った消費税(仕入税額)を差し引いた額を納付します。この仕組みを仕入税額控除といいます。
仕入税額控除は、流通や生産の各段階で多重に消費税が課されることを防ぐための仕組みです。インボイス制度下では、仕入税額控除を受けるために一定事項を記載した帳簿とインボイスの保存が必要です。
インボイス制度により必要な対応
インボイス制度導入により売り手・買い手とも制度に合わせた対応が必要になります。課税事業者は売上と仕入に分けて必要な対応を取らなくてはなりません。課税事業者だけでなく免税事業者についても対応が必要なのかについても説明します。
売り手(インボイスの発行者)が行なう対応
売り手側は、買い手側から求められればインボイスを発行しなければなりません。インボイス制度上では、売り手はインボイスを交付する義務および交付したインボイスの写しを保存する義務が課せられます。
インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者登録」が必要です。免税事業者の場合はまず課税事業者になる手続きを行なわなくてはなりません。
インボイスを求められても発行できない場合は取引が中止になったり、値引きを要求される可能性があります。取引先との関係性によって登録するか検討が必要です。課税事業者となると消費税の納税が発生しますし、納税に関する事務作業が増えるデメリットがあります。
買い手(インボイスの受取者)が行なう対応
買い手側が仕入税額控除を受けるためには原則としてインボイス又は簡易インボイスと、一定事項が記載された帳簿を保存しなければなりません。インボイスが書面の場合は書面の写しを、電子インボイスの場合はその電磁記録を約7年保存が必要です。
そのため、はじめに取引先事業者が課税事業者か免税事業者か確認しておかなくてはなりません。また、発行されたインボイスが必要な事項の記載を満たしているか、登録番号に誤りはないか、なども確認・検証する必要があります。
一方で相手がすべて中小企業であり、かつ取引の単位が1万円未満の場合はインボイスがなくても当面控除が可能です。
免税事業者が行なう対応
免税事業者はインボイス制度開始後もインボイスの発行義務はありません。しかし、取引先が課税事業者の場合、インボイスがないと仕入税額控除が受けられなくなるためインボイス発行を求められることがあります。
インボイスを発行するには課税事業者になって適格請求書発行事業者登録をする必要があります。フリーランスや個人であっても課税事業者となるか選択しなければならず、取引先と相談して判断・対応するようにしましょう。
買い手側が免税事業者の場合、登録は必要ないですし、仕入税額控除の影響も受けません。
インボイス制度による経理業務への影響
インボイス制度開始によって経理業務は煩雑になると言われています。インボイスは請求書、領収書、納品書などさまざまな様式となるため、インボイス記載事項を満たしているか十分確認しなくてはなりません。実務においてどのような点で影響があるのかみていきましょう。
取引先が適格請求書発行事業者であるかを確認する
インボイス制度では、買い手側は売り手が発行したインボイスを保存することではじめて仕入税額控除が受けられます。そのため取引先業者がインボイスを発行できる適格請求書発行事業者であるかの確認が必要になります。
確認する方法としては、自社の登録番号を通知する際に合わせて確認を取ったり、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認しましょう。
取引先が取引時点でインボイス発行事業者登録をしていない場合には、経過措置への対応を行うことで仕入税額控除が受けられます。
請求書の記載項目が変わる
前出の「従来の請求書との違い」で述べたように、今後は請求書に新たに必要項目を追加しなくてはなりません。インボイスの発行をするために必要な項目を記入できるようなテンプレートや請求書への変更が必要になります。
インボイスは様式を問わないため取引先に提示している請求書や領収書、納品書のうちどれをインボイスにするかも決めておかなくてはなりません。自社の発行するインボイスが必要な記載事項を満たしているのか確認するとともに、インボイスを受け取る場合にも確認・検証作業が必要になります。
また、買い手側はインボイスの保存が義務になりますので、約7年間保存できる保存場所の確保も必要です。
消費税の計算方法が変わる
インボイスでは商品ごとの消費税の端数処理はできなくなり、1つのインボイスについて税率ごとに1回の端数処理を行うことになります。また、課税事業者と免税事業者からの課税仕入れを区別しなければなりません。
会計処理の際は、勘定科目ごとの商品明細を分類し、税率別・課税区分別に税抜き金額を集計し、それぞれの税率をかけて税込金額を計算します。税込金額の合計がインボイスに記載された税率別の税込金額と異なる場合は、仮払消費税等で差額を調整します。
インボイス制度は消費税を正しく納税するための制度
インボイスとは、取引に係る消費税の適用税率や税額を、一定のルールによって記載した書類のことです。インボイスによってミスや不正のない、正しい消費税納税が可能になります。
インボイス制度を導入したことで、経理業務が煩雑になったり、免税事業者は課税事業者となるか判断を迫られることになるなど、インボイス制度への適応は決してスムーズに運んでいるとはいえない状況です。
しかし、当面は経過措置が取られたり、2割特例など簡易な納税額の計算方法や、補助金なども活用できます。インボイス制度の仕組みをよく理解して、正しい納税を進めていきましょう。
ビジネスに関する記事一覧
働き方の関連記事
給与・確定申告などの関連記事
ビジネスの関連記事
[PR]"好条件"の管理部門転職なら
管理部門・バックオフィスで転職するならSYNCA(シンカ)。
経理、総務、法務、労務、情シスなどの職種や細やかなスキル設定により 採用企業から一人ひとりに合ったスカウト求人が直接届きます。
まずはスキルに応じたあなたの適切な年収を無料で診断しましょう。